連載最終回は、これまで解説してきたGREATS独自のB×D×Tフレームワークを使った実践的なケーススタディだ。「電気自動車(EV)」をテーマに、T=技術、B=ビジネス、D=社会設計の3軸で立体的に分析するプロセスを紹介する。事業の「解像度を上げる」とはどういうことか、ぜひ体感してほしい。
テーマ設定:「電気自動車」をどう分析するか?
今、多くの企業が「EVシフト」という変化に注目しています。 しかし、そのほとんどが「EVという新しい技術(T)」という一面的な視点でしか捉えられていません。「高性能なEVを作らねば」「EV向けの部品を開発せねば」といった議論に終始しがちです。
しかし、GREATSは、この「電気自動車」という巨大なメガトレンドを、T・B・Dの3軸で立体的に分解します。
分析プロセス1:T軸(技術)で「バリューチェーン」を分解する
まず、T=技術の軸で、EVのバリューチェーンを分解します。 「EV」と一口に言っても、その技術は車体だけではありません。
- 川上(部品): EVの心臓部である「次世代電池」。全固体電池などの開発競争が激化しています。
- 普及の鍵: EVの利便性を左右する「充電インフラ」。これがなければEVは普及しません。
- 川下(廃棄後): 使用済み電池をどうするか。「バッテリーリサイクル」の問題。
ここから見える課題: T軸で分解するだけで、「EVを作れば終わり」ではないことが分かります。 電池の安定供給(T)、充電インフラの整備(B)、そして使用済み電池のリサイクル(D)という、T・B・Dすべての領域にまたがる複雑な課題が山積みです。
分析プロセス2:D軸(社会設計)で「競合と棲み分け」を定義する
次に、D=Design(社会設計)の軸で見ます。 EVが注目される最大の理由は、それが「脱炭素モビリティ(D)」という社会的な大義の実現手段と見なされているからです。
では、同じ「脱炭素(D)」という目的を持つ、EV以外の競合手段は何でしょうか?
- 燃料電池自動車(FCV): 水素(T)で走り、CO2を排出しません。
- クリーン燃料: 既存の内燃機関(T)を使いつつ、CO2を吸収して製造した燃料(T)で脱炭素を目指します。
ここから見える棲み分け: Dの視点で見ると、脱炭素の手段は「EV一択」ではないことが分かります。 GREATSの分析では、EVは軽量な乗用車で先行し、FCVはバスやトラックなどの商用車・重量車で、クリーン燃料は航空機や既存のインフラを活かしたい領域で、それぞれ棲み分けが進むと予測しています。
分析プロセス3:B軸(ビジネスモデル)で「真の勝者」を見極める
最後に、B=Business(ビジネスモデル)の軸で、「EVが普及した未来で、本当に儲けるのは誰か?」を考えます。
伝統的な自動車メーカー(T)でしょうか? 彼らは、高性能なEVを作るというTの競争に注力しています。
しかし、真の勝者は、B=仕組みを握るプレイヤーかもしれません。
- 充電インフラ(B): 全国の充電スポットを抑え、課金システムを握る企業
- MaaS(B): EVを使った移動データと顧客接点を抑え、移動サービス全体を提供するプラットフォーマー
- 炭素管理ソフトウェア(B/D): 企業や個人のCO2排出量を管理・取引するプラットフォーム
GREATSの視点: 歴史的に、「T(モノ)」を作るプレイヤーと、「B(仕組み・プラットフォーム)」で儲けるプレイヤーは往々にして異なります。PCの歴史で、ハードウェアメーカーよりもOSやソフトウェア企業が大きな利益を得たのと同じ構図です。
GREATSの結論:解像度を上げ、自社の「勝ち筋」を見つける
ここまで見てきたように、「電気自動車」という一つのトレンドも、B×D×Tの3軸で分析することで、その解像度は劇的に上がります。
- T軸でバリューチェーンの課題を洗い出し
- D軸で社会的な目的と競合を定義し
- B軸で未来の収益ポイント(勝ち筋)を見極める
もはや、あなたの会社が考えるべきことは「EVを作るか、作らないか」という単純な問いではありません。 「EVが普及した未来で、自社が持つ独自のT・B・Dの強みを活かし、どの領域で価値を提供するか」 これこそが、今取り組むべき「事業構想」です。
最終回にあたって:貴社のB×D×Tを構想しませんか?
5回にわたり、GREATS独自のB×D×Tフレームワークでメガトレンドを読み解く方法を解説してきました。
GREATSは、B×D×Tの視点で貴社の新規事業の「解像度」を高めるパートナーです。 私たちと一緒に、貴社の強みとメガトレンドの交差点にある「未来の事業」を構想しませんか。
(本連載 完)






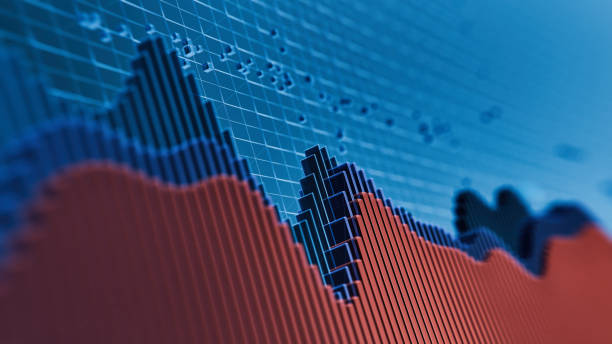



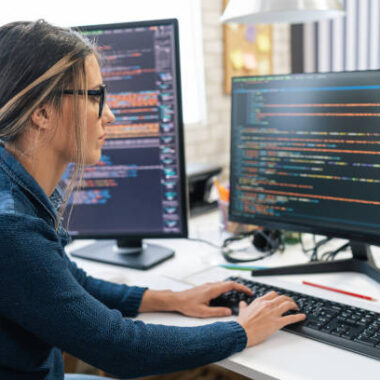














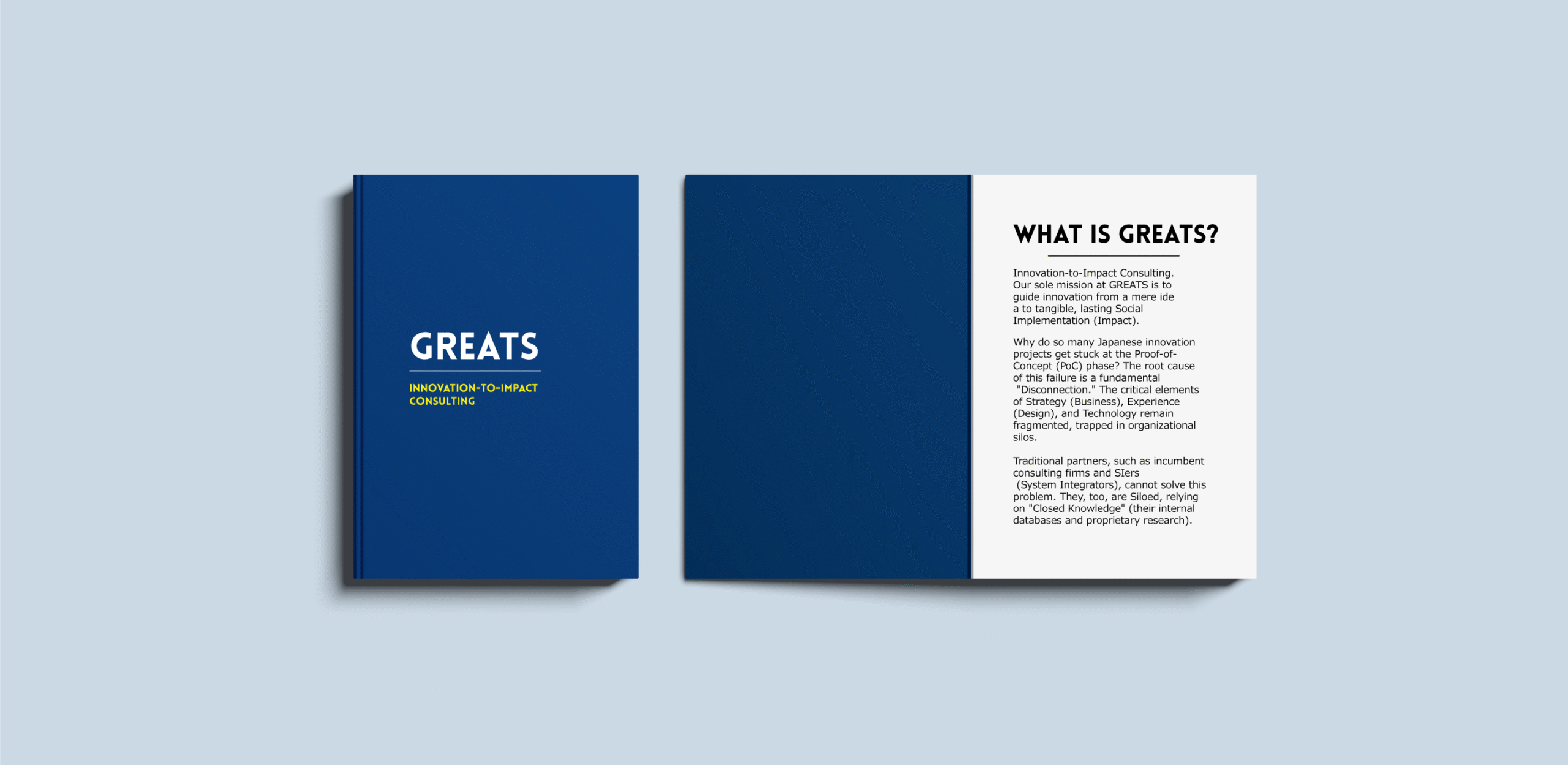
コメント