前回、イノベーションの基本形は「T=技術」と「B=ビジネスモデル」の掛け算であると解説した。しかし、現代において、このT×Bの掛け算だけでは事業は成功しない。今、あらゆるビジネスの「前提条件」となり、最強の「事業起点」ともなる第3の力、D=Designについて解説する。
T×Bだけでは「勝てない」時代
前回のおさらいです。 イノベーションの基本は、T=技術とB=ビジネスモデルの掛け算である、と解説しました。 Netflixがストリーミング技術(T)とサブスクリプション(B)を掛け合わせたように、優れたTとBの融合が、新しい顧客体験を生み出してきました。
しかし、近年はこのT×Bだけを追求した結果、さまざまな社会的な歪みが生じていることも事実です。 環境への負荷、資源の過剰な消費、あるいは人々の倫理観の変化。 こうした中で、企業や事業を見る社会の目は、かつてないほど厳しくなっています。
D (Design):未来の「大義」を決める力
そこで登場するのが、3つ目の力「D=Design(デザイン)」です。 これは、GREATSの分析レポートにおける**「3:政策や社会的価値観の変化」**に該当します。
GREATSの分析レポートでは、以下のようなトレンドがDに分類されます。
- 脱炭素エネルギー・モビリティ: 電気自動車、水素エネルギー、クリーン燃料
- 資源の循環・ロス削減: バッテリーリサイクル、食品ロス管理、サステナブルファッション
- 多様な価値観の尊重: ハラール産業、アニマルウェルフェア、メンタルヘルステック
なぜ、これらがD=Designなのでしょうか。 私たちは、Designとは単なる意匠ではなく、**「あるべき社会をどう構想し、設計するか」**という行為そのものだと捉えています。
脱炭素や資源循環は、まさに持続可能な社会システムへの**「再デザイン」です。 多様性や動物福祉(アニマルウェルフェア)は、倫理観や「より良い生き方」を「再デザイン」**する動きです。
Dは、TやBが「どうやるか」を語るのに対し、**「なぜやるのか」「どうあるべきか」**という、事業の大義や社会的な存在意義を定義する力なのです。
なぜ今「D」が最重要なのか?
GREATSの調査によれば、このDを起点とするトレンドは近年、急速に増加・加速しています。
かつて、こうしたDの領域、例えば環境対応や社会貢献は、CSR部門などが担当する「コスト」や「義務」と見なされがちでした。 しかし、今やDは、その事業の存続を許す**「前提条件(ライセンス)」であり、それ以上に、顧客がその商品やサービスを選ぶ「最大の理由(大義)」**へと変わりつつあります。
Dを無視したTとBの追求は、もはや社会から受け入れられません。 逆に、Dを起点にすることで、TとBは爆発的な推進力を得ることができるのです。
B×D×T 融合事例:テスラはなぜ「単なるEVメーカー」ではないのか?
Dの力を起点に成功した最たる例が、テスラです。 テスラの成功を、GREATS独自のB×D×Tのフレームワークで分解してみましょう。
D (大義): テスラは「脱炭素モビリティ」という巨大なD(社会的要請・あるべき姿)を事業の核に据えました。単なる速い車ではなく、「地球環境を救う」という大義からスタートしました。
T (技術): その大義を実現する手段として、「次世代電池」と「自動運転」というT(技術)に莫大な投資を集中しました。
B (仕組み): そして、既存の自動車業界のルールを破壊するB(ビジネスモデル)を採用しました。ディーラー網を介さない「D2C(直接販売)」と、自社による「充電インフラ網の構築」です。
もしテスラが、単に高性能なEVを作っただけの会社(Tだけ)であったなら。 あるいは、既存の販売網を使っていた(Bが古い)なら。 そして何より、「脱炭素」というD(大義)がなければ。 これほどの熱狂的な支持と、圧倒的な企業価値を得ることはできなかったでしょう。
テスラは、D(社会課題)を起点に、T(技術)とB(仕組み)を完璧に融合させた「B×D×T企業」なのです。
まとめ
3つの力について、整理しましょう。
- T (Technology) は、事業の可能性を決める。
- B (Business) は、事業の勝ち方を決める。
- D (Design) は、事業を行う**「意味」と「大義」**を定義する。
現代の新規事業構想は、Tから考えるのでも、Bから考えるのでもありません。 D=社会が求める「あるべき姿」から逆算して、TとBを設計する。 これが、GREATSが提唱するイノベーションのアプローチです。
次回は、このB×D×Tの3軸で、GREATSの分析レポートに掲載されているメガトレンドの全リストを紹介し、具体的な「事業のタネ」を見つける方法を解説します。










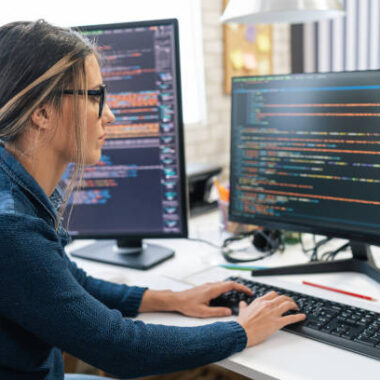













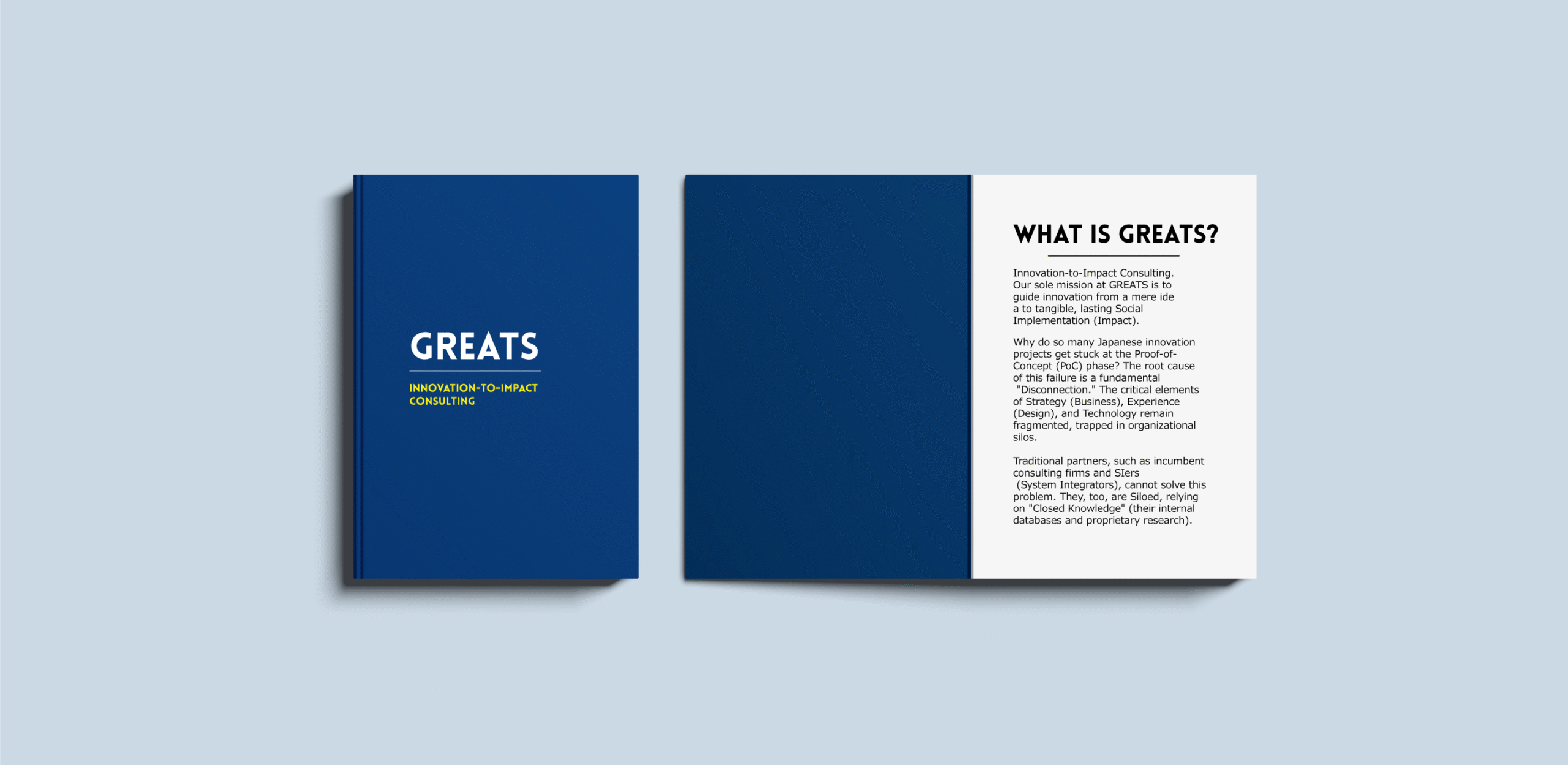
コメント