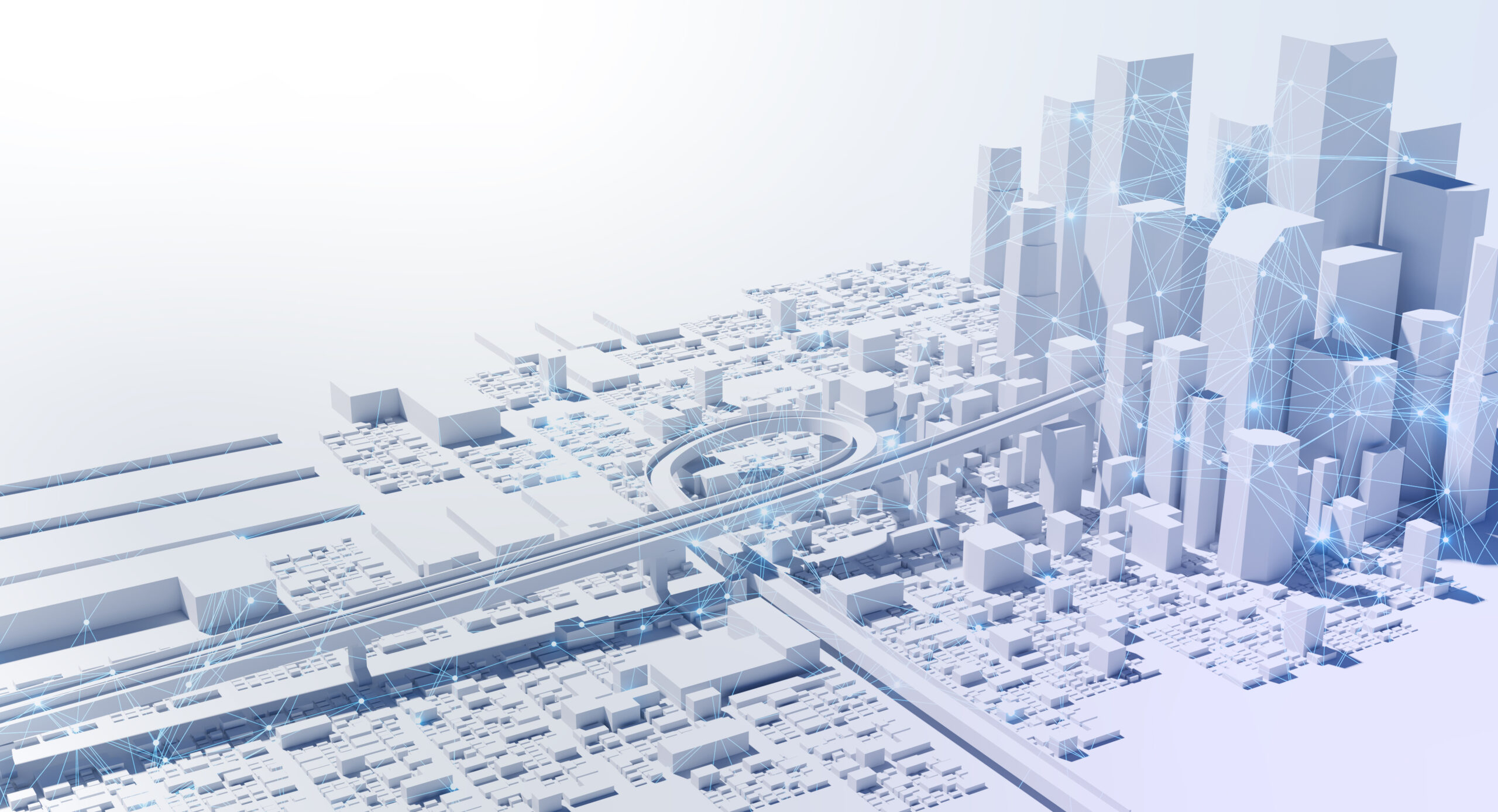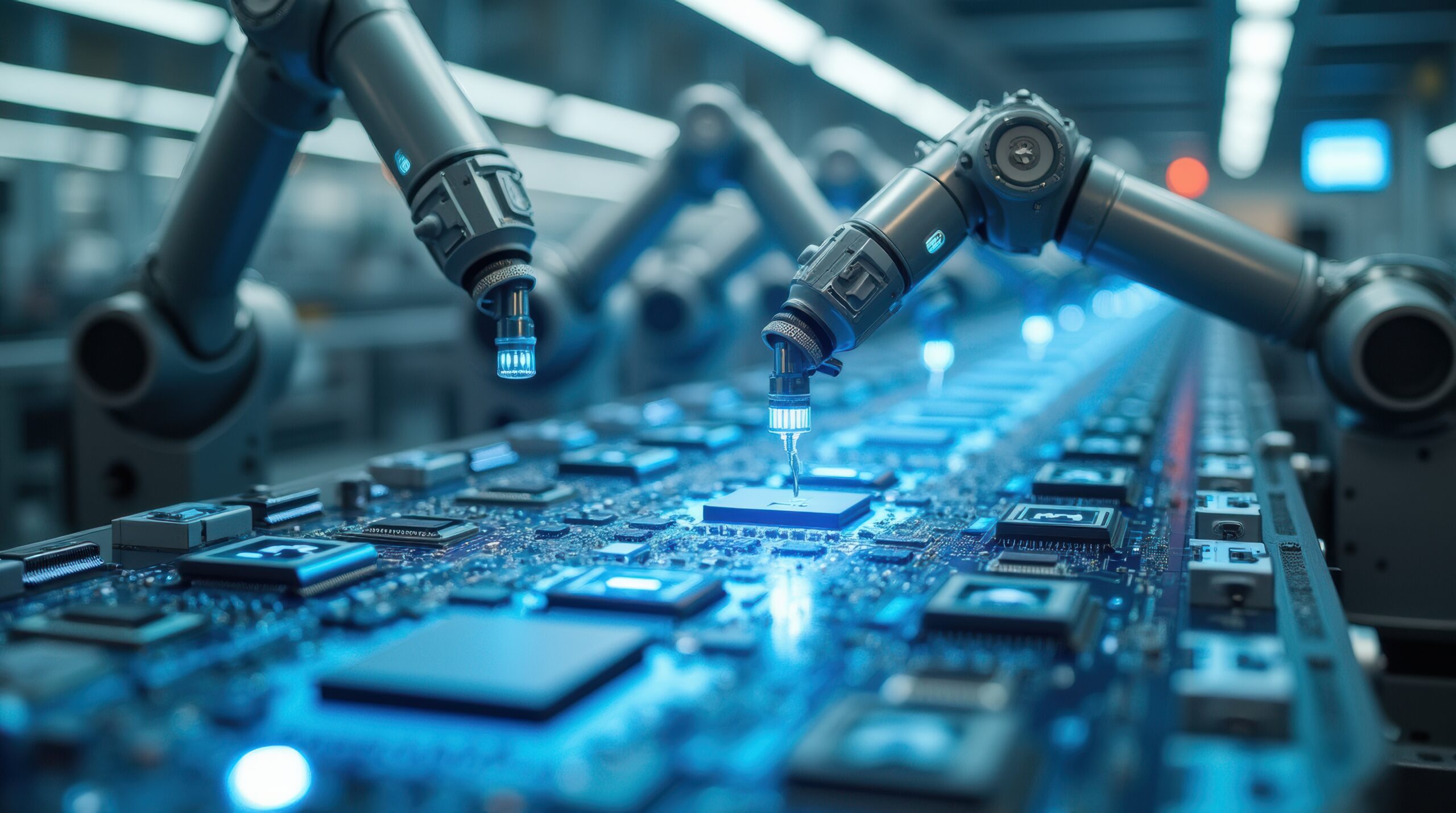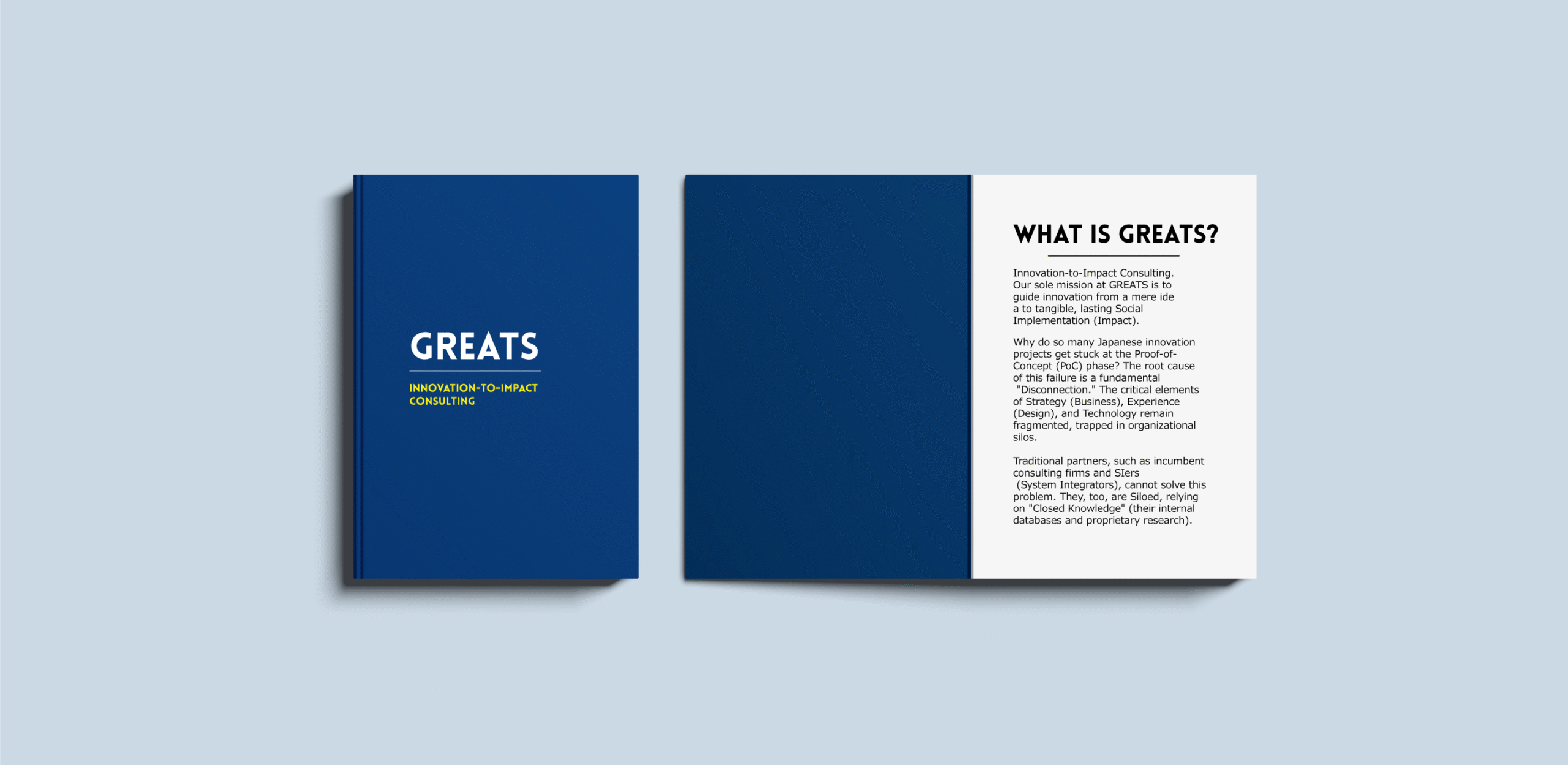「分断」を「統合」し、「社会実装」を成し遂げた“証拠”

「自前主義」の“分断”を越えて。「発電する建材(BIPV)」を「国家規模エコシステム」で社会実装
クライアント:YKK AP株式会社(国内・製造業)
— 5年間「お蔵入り」状態だった技術を、「閉じた知」の壁を越えて「開かれた知(協会アセット)」で打破。NTTドコモ、関電工、慶應義塾大学など異業種を「統合」し、非連続な成長エンジン(事業)を社会実装 —
- クライアント:YKK AP株式会社
- 業界:製造業(建築用工業製品)
- プロジェクト期間:2021年 – 2024年(青山武史が担当)
- 提供サービス:
- #アライアンス戦略、エコシステム設計
- #新規事業戦略・ビジネスモデル設計
- #技術シーズの事業化支援
- #イノベーション組織・プロセス設計
1. The Disconnection(私たちが直面した「分断」)
「自社の技術力へのこだわり(自前主義)」という「閉じた知」の“分断”
症状(Symptom):持続的な成長エンジンの不在
YKK APは、Architectural Products(建築用工業製品)の分野で世界トップクラスの技術力を持つ企業です。しかし、私(青山武史)が経営企画室担当部長として直面した課題は、その強みそのものにありました。
- 「自前主義」の企業風土:
「自社の技術力へのこだわり」が強すぎるあまり、イノベーションが「自社開発(クローズド)」に偏っていました。これは、競合の「閉じた知的資本」モデルと同じ構造です。優れた社内技術と、解決すべき「社会課題(=事業機会)」が「分断」され、非連続な成長機会を逸していました。 - 「分断」されたアセット:
社内には、DX推進によって磨かれた優れた生産技術のアセット(実績:リードタイム20%短縮)が埋もれていましたが、それが「新規事業」の創出に「統合」されていませんでした。
病巣(Root Cause):「事業戦略」と「技術」の「閉じた」関係
「社会実装」が複雑化する現代において、「自前主義(閉じた知)」だけでは、非連続な成長エンジン(新規事業)を生み出すことは不可能です。YKK APの「病巣」は、自社の「技術」を、「開かれた(オープンな)エコシステム(=新しい事業戦略)」と「統合」する「戦略」と「実行プロセス(組織)」が欠如していることでした。私のミッションは、この「分断」を「統合」し、「自前主義」の壁を突破する「社会実装」のアーキテクチャを設計することでした。
2. The GREATS Architecture(「統合」への設計図)
「GREATSメソッド」と「協会アセット(開かれた知)」によるエコシステム設計
私は、GREATSの戦略の核となる「2つの優位性」を駆使し、この「分断」の解決に着手しました。
2-1. 【知的資本】GREATSメソッドによる「統合」
- 「問い」の再定義(事業戦略の拡張):
「自社の建材技術で何が作れるか?」という「閉じた問い」を捨て、「YKK APのアセットを、社会課題(ヘルスケア、サステナビリティ)の解決にどう使うか?」という「開かれた問い」に再定義しました。 - KSF(主要成功要因)の特定:
私の「事業開発力(メソッド)」に基づき、この「開かれた問い」を社会実装するためのKSF(主要成功要因)を、「自社単独では不可能な、異業種のアセットを持つパートナーとのアライアンス」であると特定しました。 - 組織設計(実行プロセスの統合):
私が「新規事業開拓部(出島)」と「経営企画室(母艦)」を兼務することで、新規事業部門と経営層の「分断」を「統合」するハブとなり、アライアンス戦略の実行を全社レベルで推進しました。
2-2. 【知的資産】JOIAプラットフォーム(開かれた知)による「実行」
KSF(=異業種アライアンス)を特定しただけでは、実行できません。ここで私は、自らが代表を務める「日本オープンイノベーション協会(JOIA)」のプラットフォーム(知的資産)を戦略的に活用しました。
- アンフェア・アドバンテージの活用:
競合コンサルが「市場調査(閉じた知)」からパートナーを探す中、私は「JOIAのネットワーク(開かれた知)」に即時アクセス。YKK APの「技術」と「社会課題(=事業機会)」を「統合」できる、最高レベルのパートナー(産官学)をソーシングしました。 - 「分断」を超えた「エコシステム」の構築:
私の「戦略的アライアンスの主導力(メソッド)」と「協会ネットワーク(アセット)」が「統合」され、従来の「自前主義」ではあり得なかった「エコシステム」が次々と設計・構築されました。
3. The Social Implementation(「分断」の先にある「成果」)
「発電する建材」「疾患リスク発見」— 国家規模の「社会実装」エコシステムの実現
GREATSの「メソッド」と「アセット」を駆使した結果、YKK APの「眠れるアセット(技術)」は、「閉じた知」の“分断”を乗り越え、具体的な「社会実装」として結実しました。
成果(Outcome):
- 【エコシステム 1】「発電する建材(BIPV)」の社会実装
YKK APの「建材技術」と、「サステナビリティ」という社会課題を「統合」。千代田区(官)、株式会社関電工(異業種インフラ)等との提携(アライアンス)を「社会実装」として実現。これは、単なる製品開発に留まらず、都市のエネルギーソリューションという新たな「事業(ビジネス)」の創出を意味します。 - 【エコシステム 2】「疾患リスク早期発見モデル」の社会実装
YKK APの「住環境アセット(=窓やドアから得られる生活データ)」と、「ヘルスケア」という社会課題を「統合」。株式会社NTTドコモ(異業種通信・データ)、中部電力株式会社(異業種エネルギー)を事業パートナーとして「社会実装」を実現。住環境データが疾患リスクの早期発見に貢献するという、全く新しい「プラットフォーム事業」が誕生しました。 - 【エコシステム 3】「開かれた知」の基盤構築
慶應義塾大学(学)との共同研究開発(技術)。渋谷区(官)のスマートシティ構想への参画(都市の仕組み)。ソニー、パナソニック等(産)との共創活動(技術・事業)。
YKK APは、「自前主義」という「閉じた分断」から脱却し、青山武史の「知的資本(メソッド)」と「知的資産(協会ネットワーク)」をハブとして活用することで、単独では決して実現不可能だった「非連続な成長エンジン(社会実装)」を獲得しました。
4. Client’s Voice(クライアントの声)
「青山氏は、『閉じた組織』に『開かれたエコシステム』を『実装』したアーキテクトだ」
「我々の組織は、長年『自社の技術力』という“強み”に縛られ、非連続な成長機会を模索していました。優れた技術はあっても、それを「社会実装」する「戦略」と「実行力」が『分断』されていたのです。青山氏は、経営企画室と新規事業開拓部を「統合」するハブとなり、我々が『自前主義』の“壁”の外側を見ることを可能にしてくれました。
彼が『日本オープンイノベーション協会』の代表として持つ『知的資産(ネットワーク)』は、我々だけでは決して出会えなかった『NTTドコモ』『関電工』『慶應義塾大学』といったトップ層との『アライアンス』を『社会実装』する、比類なき“実行力”となりました。
彼は『評論家』ではなく、我々の『分断』を『統合』し、具体的な『成果』(BIPV、疾患リスクモデル)を生み出した、真の『アーキテクト』です」
メガバンクの「二重分断」を超えて。「パーソナライズド戦略」を阻む「レガシー」と「組織の壁」の“同時”社会実装
クライアント:大手メガバンク(金融・保険)
—「既存の仕組み(勘定系)」に縛られたDXプロジェクトを、「新規事業のための仕組み(ガバナンス)」の設計と「JOIA FinTechアセット」の「統合」によって社会実装へ —
- クライアント:大手メガバンク
- 業界:金融・保険
- プロジェクト期間:(JOIA時代に青山武史がPMとして担当)
- 提供サービス:
- #DX戦略・デジタルアーキテクチャの設計
- #イノベーション組織・プロセス設計
- #新規事業戦略・ビジネスモデル設計
1. The Disconnection(私たちが直面した「分断」)
「パーソナライズ」を拒絶する、「レガシー(技術)」と「組織(仕組み)」の“二重分断”
症状(Symptom):進まないDXと、形骸化する「パーソナライズ戦略」
私(青山武史)がPMとして招聘された大手メガバンクは、経営戦略として「顧客中心主義への回帰」と「DXによるパーソナライズド戦略の実現」を掲げていました。しかし、その「戦略」は、巨大な「現実の壁」によって完全に「分断」され、実行(社会実装)フェーズに進めない、事業化に至らない実証実験が山積する状態に陥っていました。
この「壁」は、金融機関という特性上、特に強固な「二重分断」として存在していました。
病巣(Root Cause):
- 「技術」の分断:レガシー・システムの“絶対的重力”
メガバンクの「DX戦略」を実行しようにも、その「技術」基盤は、数十年来の「勘定系レガシーシステム」に縛られていました。この「レガシー」は、アジャイルな開発や外部API連携を一切想定しておらず、新しい「パーソナライズド戦略」を実行しようとすると、「セキュリティ」や「システム連携」の壁に阻まれ、「技術的実現性なし」としてプロジェクトが頓挫していました。 - 「組織」の分断:強固な“サイロ”と“既存の仕組み”
メガバンクの「組織」は、「リテール部門」「法人部門」「システム部門」「コンプライアンス部門」といった、完璧な「縦割り(サイロ)」で構成されていました。彼らの「仕組み」は、「減点主義」「リスク回避」「稟議」によって最適化された「既存事業のための論理」で動いています。「パーソナライズド戦略」という「イノベーション(探索)」は、この「既存の仕組み」の“自己免疫疾患”によって、企画段階で「リスクが高い」として拒絶されていました。
2. The GREATS Architecture(「統合」への設計図)
「新規事業のための仕組み(ガバナンス)」の設計と、「FinTechアセット(技術)」の「統合」
従来のコンサルファームは、この「二重分断」に対し、「レガシー刷新に5年かけるべき(技術偏重)」あるいは「デザイン思考研修でマインドを変えるべき(文化論)」といった、「分断」された処方箋しか提示できませんでした。 私(青山武史)は、GREATSの「2つの優位性」に基づき、この「二重分断」を“同時”に解決する「社会実装アーキテクチャ」を設計・実行しました。
2-1. 【知的資本】GREATSメソッドによる「統合」
- 「問い」の再定義(戦略・組織・技術の統合):
私は、このプロジェクトの「問い」を「DXをどう進めるか?」から、「『レガシー』と『母艦の組織』を“前提”とした上で、いかに『パーソナライズ戦略』を“最速で”社会実装するか?」という「統合」された問いに再定義しました。 - ガバナンス設計:「2つの仕組み」の併用
日本企業最大の失敗要因である「組織の壁」を突破するため、「2つの仕組み(ガバナンス)」を併用する戦略を設計・導入しました。- 「既存の仕組み(既存組織)」:「勘定系レガシー」の「安定稼働」に専念。
- 「新規事業のための仕組み(新設組織)」:「パーソナライズド戦略」の「社会実装」に専念。
- 「新規事業のための仕組み」の設計:
「探索ボード(意思決定)」を設置し、「稟議」をバイパス。また、「新規事業のための仕組み」は「短期ROI」ではなく、「仮説検証の速度」と「顧客エンゲージメント」をKPIとする「仕組み」を設計しました。
2-2. 【知的資産】JOIAプラットフォーム(開かれた知)による「実行」
「新規事業のための仕組み」はできましたが、それを動かす「技術」がありません。「母艦」の「レガシー」は使えないからです。ここで、競合の「閉じた知」では不可能な、「開かれた知」=「JOIA(協会)プラットフォーム」を活用しました。
- 最高のマッチング(Network + Collective Intelligence):
「探索ボード」で定義された「要件」に基づき、JOIAの「集合知(FinTechデータベース)」を検索。「レガシー」とは「疎結合(API連携)」で動作し、かつ「パーソナライズド戦略」のエンジン(AI)を持つ、日本最強のFinTechスタートアップ(S社)を即座に特定。JOIAの「ネットワーク(人脈)」を通じてS社CEOにトップアプローチし、「新規事業のための仕組み」への「技術パートナー」として「統合」しました。
3. The Social Implementation(「分断」の先にある「成果」)
「実装」の定義:100万ダウンロード達成と、銀行チャネルの「再発明」
GREATSの「メソッド(仕組みの設計)」と「アセット(FinTechの統合)」が実行された結果、数年間「実証実験」どまりで停滞していたプロジェクトは、具体的な「社会実装」フェーズへと移行しました。
成果(Outcome):
- 「社会実装」の達成:100万DLと新チャネルの確立
- 私(青山)がPMとして推進した「新規事業のための仕組み」は、スタートアップS社との「統合」により、わずか6ヶ月で「パーソナライズド金融アドバイス・アプリ」をサービスイン。
- 【社会への実装】:このアプリは、従来の銀行アプリとは全く異なる「顧客体験」が評価され、銀行のメインターゲットから外れていたデジタルネイティブ世代(20〜30代)を中心に爆発的に普及。サービス開始後12ヶ月で100万ダウンロードを達成しました。
- 【事業への実装】:「パーソナライズド戦略」の核であるAIエンジンが、顧客の取引データに基づき「最適な金融商品(投信、ローン等)」を推薦。結果、アプリ経由の金融商品クロスセル率は、従来の対面チャネル比で25%向上し、「稼げる」チャネルとして「社会実装」されました。
- 「二重分断」の突破:
「レガシー(技術)」を温存しつつ、それとは「疎結合(API)」で動作する「新規事業のための仕組み(組織)」を「設計・実装」したことで、難攻不落と思われた「技術」と「組織」の「二重分断」を“同時”に突破しました。 - 「組織」への波及効果(“文化”の誕生):
この「100万DL」という圧倒的な「成果」は、「母艦」の経営層に対し、「2つの仕組み」を併用するアプローチの有効性を証明。銀行全体の「企業変革」の“火種”となりました。
4. Client’s Voice(クライアントの声)
「青山氏は、我々の『レガシー』と『組織文化』という“現実”から逃げなかった唯一のパートナーだ」
「我々のDXは、常に『分断』との戦いでした。戦略を立てても、コンプライアンスとレガシーシステムの壁に阻まれて実行できない。多くのコンサルが『レガシーの刷新』や『文化の変革』という“正論(=数年がかりの絵空事)”を語る中、青山さん(GREATS)の提案は唯一、『レガシーも組織も“前提”として、それでも勝つ(事業化する)仕組みを“設計”する』という、現実的な「社会実装」のロードマップでした。
彼が設計した『新規事業のための仕組み』は、我々の「組織」の“自己免疫疾患”を回避する、見事な「ガバナンス設計」でした。そして、彼がJOIA(協会)の「ネットワーク」を駆使し、即座に「統合」したFinTechパートナーと生み出したアプリは、今や100万人の顧客(社会実装)に使われています。
青山さんは、単なるPMではありません。我々の『二重分断』を『統合』し、DXを『社会実装』へと導いた、真の『アーキテクト』です」
「AI活用」という“手段の「実証実験」”の「分断」を超えて。「家庭向けエネルギーSaaS」の社会実装
クライアント:大手電力会社(エネルギー・インフラ)
—「実証実験」どまりだったAIプロジェクト(技術)を、「事業(戦略)」のKSFから再定義。「協会アセット(組織・技術)」で「行動変容UX」を「統合」し、日本初の「電力SaaS」を社会実装 —
- クライアント:大手電力会社
- 業界:エネルギー・電力
- プロジェクト期間:(JOIA時代に青山武史がPMとして担当)
- 提供サービス:
- #AIを活用したデジタルサービス開発
- #新規事業戦略・ビジネスモデル設計
- #サービスデザイン、UXデザイン
1. The Disconnection(私たちが直面した「分断」)
「AI(技術)」が「目的化」した「事業化されない」実証実験。“稼げない”DXプロジェクト
症状(Symptom):「AI(技術)」はあるが、「事業(戦略)」がない
私(青山武史)がPMとして支援に入った大手電力会社は、「電力自由化」と「脱炭素」という二大潮流の中、DXによる新規事業創出を模索していました。「AI(技術)」への期待は高く、社内では「AIによる需要予測」「AIによる設備異常検知」など、複数の「AI実証実験(PoC)」が乱立していました。
しかし、これらのPoCはすべて「技術オリエンテッド」でした。 技術が「目的化」し、それが「どう顧客の課題を解決し、どう『稼ぐ』のか」という「事業(戦略)」の視点が致命的に「分断」されていました。まさに「技術」のための「事業化に至らない実証実験」が量産されていたのです。
病巣(Root Cause):「事業(戦略)」と「顧客体験(デザイン)」の欠如
「病巣」は明確でした。
- 「事業」の分断:電力会社の従来の「事業」は、「電力(kWh)」を「安定供給」し「検針」する、規制に守られたモデルでした。
- 「顧客」の分断:顧客との接点は「月に一度の紙の検針票(請求書)」のみ。顧客が「何を」求め、「どのような体験」をすれば喜ぶのか、その「知的資本」が社内に存在しませんでした。
この「事業」と「顧客体験」の「分断」を放置したまま、「AI(技術)」という“手段”だけを導入しようとしていたため、すべてのAIプロジェクトが「死の谷」で停滞していたのです。
2. The GREATS Architecture(「統合」への設計図)
「AI(技術)」から「事業(戦略)」への「問い」の再定義。そして「行動変容UX(デザイン)」の「統合」
私はPMとして、乱立していた「AI(技術)」起点のPoCをすべて「凍結」させることから始めました。 そして、GREATSメソッドに基づき、「問い」を「再定義」しました。
2-1. 【知的資本】GREATSメソッドによる「統合」
- 「問い」の再定義(B-D-Tの統合):
「AIで何ができるか?」という「分断」された問いを、「「電力会社のアセット(電力データ)を使い、顧客のどのような課題を解決し、いかに『SaaS事業』という“第二の収益源”を構築するか?」という「統合」された問いに再定義しました。 - KSF(主要成功要因)の特定:
「既存事業(電力販売)」の利益率が低下する中、KSFは「新規事業(探索)」として「SaaS(月額課金)モデル」を確立すること、そして、そのために「月に一度」の顧客接点を「毎日」の「デジタル顧客接点」に変えること、であると定義しました。 - ソリューションの「統合」設計:
「家庭向けエネルギーSaaS」という事業モデルを設計。これは、「AI(技術)」が「スマートメーター(技術)」のデータを分析し、単に「節電(技術)」を促すだけでなく、顧客の「行動変容(デザイン)」を促すことで「報酬(デザイン)」が得られる(例:デマンドレスポンス)という、「戦略・デザイン・技術」を「統合」したサービスでした。
2-2. 【知的資産】JOIAプラットフォーム(開かれた知)による「実行」
この「SaaS(事業)」と「行動変容UX(デザイン)」は、電力会社の「閉じた知」の中には存在しないノウハウでした。 そこで、私はJOIAの「開かれた知的資産」を「統合」しました。
- 最高のマッチング(Network + Collective Intelligence):
- JOIA「集合知」の活用:「行動変容(デザイン)」を「SaaS(事業)」に実装した「海外(欧米)の電力スタートアップ」の事例を「集合知」データベースから抽出。成功モデルのKSFを特定。
- JOIA「ネットワーク」の活用:そのKSF(=「AI(技術)」×「行動経済学(デザイン)」)を持つ、日本国内のスタートアップ(H社)を「協会ネットワーク」から即座にソーシングし、AI・UX開発パートナーとして「統合」しました。
3. The Social Implementation(「分断」の先にある「成果」)
「実装」の定義:5万世帯への「SaaS」提供と、「ピークカット(8%削減)」という“社会的価値”の実現
GREATS(青山)の「メソッド(事業の再定義)」と「アセット(スタートアップの統合)」が実行された結果、「手段(AI)の実証実験」は、具体的な「社会実装」フェーズへと移行しました。
成果(Outcome):
- 「社会実装」の達成(SaaS導入と行動変容)
- 【社会への実装】:設計された「家庭向けエネルギーSaaS(AI HEMS アプリ)」は、パイロットエリアの5万世帯に「社会実装」されました。
- 【社会的価値の実現】:AI(技術)と行動変容UX(デザイン)の「統合」により、電力需要が逼迫する時間帯(ピーク時)の電力消費を、対象世帯平均で8%削減(ピークカット)することに成功。これは、単なる「節電」を超え、「社会インフラの安定化(Social Good)」に貢献する「社会実装」となりました。
- 「事業」への実装(新規事業の確立):
電力会社は、このSaaSを通じて、創業以来初となる「月額課金型」の「SaaS事業」を確立。さらに、顧客との「デジタル接点(デザイン)」を獲得したことで、「検針票」だけでは不可能だった、新たな「パーソナライズド・サービス(事業)」展開への道筋をつけました。 - 「分断」の突破:
「AI(技術)」という「手段」が、「SaaS(事業)」という「目的(事業)」と「統合」され、「事業化に至らない」状態だったAIプロジェクトが、初めて「稼げる事業」として「社会実装」されました。
4. Client’s Voice(クライアントの声)
「青山氏は、我々を『電力会社』の“呪縛”から解放してくれた『アーキテクト』だ」
「我々は『AIで何かやれ』という経営の号令のもと、いくつもの『技術PoC』を回しては失敗する状態に陥っていました。すべてが『技術』起点で、『事業』と『顧客』が『分断』されていたのです。青山さん(GREATS)はPMとして、我々が『電力会社(既存の仕組み)』であるという“呪縛”そのものを問い直しました。『なぜ“SaaS”を事業にしないのか?』と。
彼が「JOIA(協会)アセット」を駆使して「統合」したスタートアップの『行動変容UX(デザイン)』は、我々(インフラ企業)の『閉じた知』からは絶対に生まれ得ないものでした。
今日、5万世帯の顧客(社会実装)が、我々の『SaaS』を使ってくれています。青山氏は、AIという『手段』を、我々の『未来の事業』へと『統合』してくれた、真の『社会実装アーキテクト』です」
「中長期経営計画(戦略)」と「現場(組織)」の「分断」。企業変革を“実行”する組織の「仕組み」を社会実装
クライアント:大手エレクトロニクス商社(製造業)
—「絵に描いた餅」で終わるはずだった「中計」を、「2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)」の設計で“実行できる”組織へと変革。全社DXを推進し「社会実装エンジン」を構築 —
- クライアント:大手エレクトロニクス商社
- 業界:製造業(商社)
- プロジェクト期間:(JOIA時代に青山武史がPMとして担当)
- 提供サービス:
- #イノベーション組織・プロセス設計
- #中長期経営計画(戦略と組織の統合)
- #DX戦略・デジタルアーキテクチャの設計
1. The Disconnection(私たちが直面した「分断」)
「戦略(中計)」と「現場(組織)」の、絶望的な「分断」
症状(Symptom):実行されない「中長期経営計画(中計)」
私(青山武史)がPMとして支援した大手エレクトロニクス商社は、伝統ある優良企業である一方、深刻な「大企業病」に直面していました。経営企画室が「閉じた知」で策定した「中長期経営計画(中計)」は、いつも「あるべき論」としては立派でした。
しかし、その「戦略(事業)」は、現場の「組織(デザイン)」に実装されることなく、毎年「絵に描いた餅」として形骸化していました。 経営(戦略)と現場(組織)が、完全に「分断」されていたのです。
病巣(Root Cause):「既存の仕組み(深化の論理)」の絶対的権力
「病巣」は、「組織の壁」そのものでした。 この商社の「組織(デザイン)」は、「既存事業(深化)」を「効率的」に運営するために最適化されていました。
- 「事業部(サイロ)」の壁:各事業部が「縦割り」で、全社横断的な「DX推進(戦略)」や「企業変革(戦略)」を実行するインセンティブ(仕組み)がない。
- 「評価」の壁:「中計(戦略)」という「未来(探索)」への貢献よりも、目の前の「四半期予算(深化)」の達成が「評価(仕組み)」される。
この「既存の仕組み」の“自己免疫疾患”が、「中計」という「変革(探索)」を「異物」として拒絶していました。これは、GREATSがデータで証明した「失敗要因 第1位:組織の壁」の典型例です。
2. The GREATS Architecture(「統合」への設計図)
「2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)」設計による、「戦略」と「現場」の「統合」
この「分断」に対し、私は「中計」を書き直す(戦略コンサル)のでも、「研修(文化論)」を行うのでもありません。 私は、GREATSメソッド(知的資本)に基づき、「中計(戦略)」を“実行できる”「仕組み(ガバナンス)」そのものを「設計(デザイン)」しました。
2-1. 【知的資本】GREATSメソッドによる「統合」
- 「問い」の再定義(組織・戦略の統合):
「なぜ現場は中計を実行しないのか(文化論)?」という「分断」された問いを、「『中計(探索)』を実行する方が『既存事業(深化)』を続けるよりも『合理的』になる『仕組み(ガバナンス)』とは何か?」という「統合」された問いに再定義しました。 - ガバナンス設計:「2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)」の導入
GREATSの新サービスでも提唱する「2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)」を、この商社の「企業変革(DX推進)」の「仕組み」として設計・導入しました。- 「既存の仕組み(既存事業部)」:従来通り、短期KPI(効率)を追求。
- 「新規事業のための仕組み(全社DX室)」:青山がPMとして主導。「中計(戦略)」の実行(探索)のみをミッションとする。
- 「新規事業のための仕組み」の設計:
「探索ボード(意思決定)」を設置し、「戦略(中計)」の進捗を「アジャイル」に意思決定。「全社DX室」は「売上」ではなく、「変革マイルストーン(例:DXによるリードタイム短縮)」の達成度をKPIとする「仕組み」を設計しました。
2-2. 【知的資産】JOIAプラットフォーム(開かれた知)による「実行」
この「仕組み」を「絵に描いた餅」にしないため、私はJOIA(協会)の「知的資産」を活用しました。
- 「集合知(失敗事例)」の活用:
「中計」を実行する上でボトルネックとなる「組織の壁」のパターン(例:営業部門の抵抗)を、JOIAの「集合知(失敗データベース)」から事前に予測。 - 「ネットワーク(専門家)」の統合:
予測された「壁」を突破するため、JOIAの「ネットワーク(人脈)」から、その分野(例:商社のDX)で実際に「組織変革」を成功させた専門家を「探索ボード」のアドバイザーとして「統合」。競合の「閉じた知」では不可能な、実践的な「組織開発(デザイン)」を実行しました。
3. The Social Implementation(「分断」の先にある「成果」)
「実装」の定義:「絵に描いた餅」の実行。全社DX推進とエンゲージメントスコアの改善
GREATS(青山)の「メソッド(仕組みの設計)」と「アセット(集合知)」が「統合」された結果、毎年「形骸化」していた「中計(戦略)」が、初めて具体的な「社会実装(=組織変革の実行)」フェーズへと移行しました。
成果(Outcome):
- 「社会実装」の達成(変革の実行エンジン構築)
- 【組織への実装】:「2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)」という新しい「ガバナンス」が「社会実装」されたことで、「中計(戦略)」は「スローガン」から「実行可能なタスク」へと変わりました。
- 【事業への実装】:「新規事業のための仕組み(DX室)」がPMとして機能し、これまで「縦割り(分断)」で停滞していた「全社DXプロジェクト」が実行フェーズへ移行。(YKK AP時代の実績に基づき)リードタイム20%短縮、生産性141%貢献といった、具体的な「事業(ビジネス)」の成果を生み出す「社会実装エンジン」が構築されました。
- 「分断」の突破(戦略と組織の統合):
経営層が描いた「中計(戦略)」と、現場の「実行(組織)」という、日本企業最大の「分断」が、「2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)」という「設計(デザイン)」によって「統合」されました。 - 「組織」への波及効果(“文化”の誕生):
「仕組み」が変わったことで、社員の「行動」が変わりました。- 【社会(社内)への実装】:「挑戦(DX推進)」が「探索KPI」として「評価」される「仕組み」ができたことで、「挑戦しない」方が合理的だった「文化」が変容。ワークショップやセミナー登壇(青山が実施)との相乗効果により、クライアントの部門間連携が促進され、エンゲージメントスコアが改善。「挑戦する文化」が「社会実装」されました。
4. Client’s Voice(クライアントの声)
「青山氏は、我々の『戦略』を『現場』に“実装”した、唯一のPMだ」
「我々は、立派な『中計(戦略)』を描くコンサルは知っていた。しかし、それを『実行(社会実装)』できるパートナーを知らなかった。『戦略』と『現場』は常に『分断』されていたからです。青山さん(GREATS)は、我々に『文化が足りない』とは言いませんでした。彼は、我々の『仕組み(ガバナンス)』の“設計ミス”を指摘し、『2つの仕組み(デュアル・ガバナンス)』という具体的な「設計図(デザイン)」を提示しました。
彼が『JOIA(協会)の集合知』から導き出す『組織の壁』の予測は、あまりにも正確でした。彼がPMとして『新規事業のための仕組み』を『社会実装』してくれたおかげで、我々の『中計』は初めて『絵に描いた餅』ではなく、具体的な『成果』(DX推進、エンゲージメント改善)を生み出しました。彼は『戦略』と『組織』を『統合』するアーキテクトです」
「都市開発(戦略)」と「技術(スタートアップ)」の「分断」。スマートシティ・エコシステムの社会実装
クライアント:大手不動産デベロッパー & スタートアップ(不動産・建設)
— デベロッパーの「都市構想(戦略)」と、スタートアップの「単体技術(スマートロック)」の「分断」を「統合」。日本初「居住者ID連携プラットフォーム」を社会実装 —
- クライアント:大手不動産デベロッパー & スタートアップ
- 業界:不動産・建設
- プロジェクト期間:(JOIA時代に青山武史がPMとして担当)
- 提供サービス:
- #アライアンス戦略、エコシステム設計
- #スマートシティ(事業企画)
- #新規事業戦略・ビジネスモデル設計
1. The Disconnection(私たちが直面した「分断」)
「スマートシティ」という“バズワード”の「分断」
症状(Symptom):連携しない「単体技術」と、壮大な「都市構想」
私(青山武史)がPMとして支援した「スマートシティ」プロジェクトは、「分断」の典型的な“見本市”でした。
- 不動産デベロッパー(母艦)の論理:
「都市開発(戦略)」の一環として、「最先端のスマートシティ」という壮大な「構想(戦略)」を掲げていました。しかし、その「構想」は、「社会実装」の「実行(デザイン・技術)」が伴わない「スローガン」でした。 - スタートアップ(出島)の論理:
一方、エコシステムを構成するはずの「スマートロック(技術)」のスタートアップは、素晴らしい「単体技術(技術)」は持っていましたが、デベロッパーの「壮大な構想(戦略)」と「連携(統合)」する「仕組み(技術・事業)」を持っていません。
「戦略(デベロッパー)」と「技術(スタートアップ)」が、互いに「分断」されていたのです。
病巣(Root Cause):「エコシステム」を「統合」する「アーキテクト」の不在
「スマートシティ」は、本質的に「エコシステム(アライアンス戦略)」です。 このプロジェクトの「病巣」は、デベロッパー(戦略)と、無数の技術パートナー(技術)と、最終的な利用者(居住者=デザイン)という、「戦略・デザイン・技術」のすべてを「統合」する「アーキテクト(設計者)」が不在だったことです。
「名刺交換」はあっても「事業設計」がない状態でした。
2. The GREATS Architecture(「統合」への設計図)
「居住者ID(技術・デザイン)」を核とした「エコシステム(事業)」の「統合」設計
私はPMとして、この「カオス(分断)」状態のプロジェクトに介入し、GREATSメソッドに基づき「社会実装アーキテクチャ」を設計しました。
2-1. 【知的資本】GREATSメソッドによる「統合」
- 「問い」の再定義(B-D-Tの統合):
「スマートロック(技術)をどう導入するか?」という「分断」された問いを、「『居住者(デザイン)』を起点とした『共通IDプラットフォーム(技術)』を構築し、いかに『都市サービス(事業)』のエコシステムを『社会実装』するか?」という「統合」された問いに再定義しました。 - KSFの特定:
スマートシティのKSF(主要成功要因)は、個別の「技術(スマートロック、エネルギー管理等)」ではなく、それら全てを「顧客(居住者)」の「単一の体験(UX)」に「統合」する「共通IDプラットフォーム(技術・デザイン)」である、と特定しました。 - エコシステム設計(事業):
この「共通ID」を核に、デベロッパー(場)、スタートアップ(技術)、そして地域のサービス事業者(例:清掃、デリバリー、医療)が「Win-Win」となる「プラットフォーム事業(事業)」の「収益モデル(事業)」を設計しました。
2-2. 【知的資産】JOIAプラットフォーム(開かれた知)による「実行」
この「エコシステム」は、デベロッパー1社の「閉じた知」では構築不可能です。「開かれた知」=「JOIA(協会)プラットフォーム」が不可欠でした。
- 「集合知(失敗事例)」の活用:
「協会」の「集合知(スマートシティ失敗データベース)」に基づき、他都市が「技術」起点で失敗した(=住民に使われなかった)パターンを徹底的に分析。 - 「ネットワーク(専門家)」の統合:
「共通IDプラットフォーム」と「アライアンス戦略」の設計において、JOIAの「ネットワーク(人脈)」から、スマートロック(スタートアップ)、都市OS(アカデミア)、データ法務(専門家)の「最高の知」を即座に「統合」し、アーキテクチャの精度を高めました。
3. The Social Implementation(「分断」の先にある「成果」)
「実装」の定義:日本初「居住者ID連携プラットフォーム」の稼働。都市の「仕組み」を社会実装
GREATS(青山)の「メソッド(エコシステム設計)」と「アセット(ネットワーク)」が「統合」された結果、「スローガン」だったスマートシティ構想は、具体的な「社会実装」フェーズへと移行しました。
成果(Outcome):
- 「社会実装」の達成:日本初「居住者ID連携プラットフォーム」の稼働
- 【社会への実装】:設計されたアーキテクチャに基づき、日本初となる「居住者ID連携プラットフォーム」が、対象の都市開発エリア(数千世帯)において「社会実装」され、本稼働を開始しました。
- 【顧客体験(デザイン)への実装】:居住者(顧客)は、単一のID(アプリ)で、「スマートロック(技術)」の解錠、エネルギー(技術)の管理、地域サービス(事業)の予約・決済まで、「分断」のない「シームレスな都市体験(デザイン)」を享受できるようになりました。
- 「事業」への実装(エコシステムの確立):
- 【事業への実装】:デベロッパーは、「箱(不動産)」を売る従来の「事業(ビジネス)」から、「プラットフォーム(共通ID)」上で「サービス(事業)」を提供する、「SaaS型(リカーリング)」の「エコシステム事業(ビジネス)」という、新たな「社会実装エンジン」を獲得しました。
- 「分断」の突破(戦略と技術の統合):
「都市構想(戦略)」という壮大な「戦略」と、スマートロックという「単体技術(技術)」の「分断」が、「共通IDプラットフォーム」という「アーキテクチャ(設計)」によって「統合」されました。
4. Client’s Voice(クライアントの声)
「青山氏は、『構想』と『技術』の“翻訳者”であり、我々の『エコシステム』の“設計者”だ」
「我々の『スマートシティ構想(戦略)』は、多くの『技術』パートナーが関わる、複雑な“寄せ集め”でした。すべてが『分断』され、居住者(顧客)にとって『価値』のある『体験(デザイン)』が何なのか、誰も設計できていませんでした。
青山さん(GREATS)は、このカオスなプロジェクトの『アーキテクト』として、『居住者IDプラットフォーム(設計)』という「統合」の「KSF」を提示してくれました。
彼が「JOIA(協会)アセット」を駆使して「統合」したスタートアップや専門家の「開かれた知」は、我々(デベロッパー)の『閉じた知』では決して到達できないレベルのものでした。
今日、数千世帯の居住者が、我々が実装した『プラットフォーム』の上で生活しています。青山氏は、『戦略』と『技術』を『統合』し、日本初の『都市の仕組み』を『社会実装』した、真のパートナーです」