「価値」と「価格」の「分断」。「事業実現」の核心である「稼ぐ仕組み」の設計論。
「ユーザーは集まったが、儲からない」。これは、「顧客が感じる価値」と「収益化(マネタイズ)」が**バラバラな状態(分断)**になっている、イノベーション失敗の典型例です。「収益化は後で考える」というアプローチは事業の危機を招きます。本稿では、「価値」と「価格」を「統合」し、「事業実現」のエンジンとなる「収益モデル」を設計する手法を解説します。
執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部
【目次】
1. はじめに:「稼げない」イノベーションは「事業実現」ではない
- 1-1. 「ユーザー数」という“幻想”と、「事業化」という“現実”
- 1-2. 「収益化」を後回しにするという「分断」
- 1-3. 本稿の論点:「価値」と「価格」の「統合」
2. データ分析:データが示す「事業失敗」の本質
- 2-1. グローバルな「事業失敗要因」という「客観的証拠」
- 2-2. 失敗要因1位:「市場ニーズの欠如」
- 2-3. 失敗要因2位:「資金枯渇」
- 2-4. 論考:これらは全て「収益設計」の「分断」である
3. 「収益化(事業)」が「分断」される3つのパターン
- 3-1. 分断 1:「事業と体験の分断」—「ユーザー獲得」を優先し、「収益化」を後回しにする
- 3-2. 分断 2:「戦略と戦略の分断」—「単一」の収益源に依存し、成長を最大化できない
- 3-3. 分断 3:「体験と戦略の分断」—「価格」が「価値」と一致していない
4. GREATSの処方箋:「価値(体験)」を「価格(事業)」に「統合」する手法
- 4-1. 「問い」の再定義:「いくらか」ではなく「何の対価か」
- 4-2. 手法1:収益化戦略 — 価格設定と収益モデルの設計
- 4-3. 手法2:顧客生涯価値の最大化プラン
5. 結論:「収益化設計」こそが、「事業・体験・技術」統合の“要”である
記事本文
1. はじめに:「稼げない」イノベーションは「事業実現」ではない
1-1. 「ユーザー数」という“幻想”と、「事業化」という“現実”
「月間アクティブユーザー100万人突破」「アプリダウンロード数500万件」。
新しい事業の現場では、しばしばこのような「ユーザー数」の増加が「成功」として語られます。しかし、これは「事業実現」の「始まり」ではあっても、「ゴール」ではありません。
どれほど多くのユーザーを集めても、どれほど素晴らしい「顧客体験」を提供していても、その活動が「持続可能な収益」を生み出さなければ、そのプロジェクトは「資金枯渇」によって必ず事業の危機を迎えます。
「稼げない」イノベーションは、持続可能性を持たない「ボランティア」であり、GREATSが定義する、自立して成長できる「事業実現」ではありません。
1-2. 「収益化」を後回しにするという「分断」
しかし、新しい事業の現場では、「収益化は後で考える」という危険な考え方が広がっています。
「まずはユーザー獲得(体験)に全力を注げ。収益化(事業)は、その“後”で考えればいい」
これは、「顧客が感じる価値」と「収益化」を、意図的に**バラバラの状態(分断)**にするアプローチです。
この「分断」こそが、イノベーションが「事業化に至らない実証実験」で終わる、最大の要因の一つです。先日私たちが発表した「イノベーション失敗レポート」でも、「収益化戦略の欠如」は、「組織の壁」に次ぐ「失敗要因の第2位」を占めています。
1-3. 本稿の論点:「価値」と「価格」の「統合」
本稿では、この「収益化戦略の不在」という分断に焦点を当てます。
まず、グローバルなデータに基づき、「収益化の設計」の失敗が、いかに事業にとって「致命傷」であるかを明らかにします。
次に、「収益化」がバラバラな状態になる3つの典型的な失敗パターンを、事例で解明します。
そして最後に、この分断を「統合」し、「良いサービス」を「稼げる事業(事業実現)」へと転換するための、GREATSの「収益モデル設計」手法を提示します。
2. データ分析:データが示す「事業失敗」の本質
2-1. グローバルな「事業失敗要因」という「客観的証拠」
「収益化」の分断が、いかにプロジェクトの「死」に直結しているか。
その「客観的証拠」として、米国の調査会社が発表している「スタートアップが失敗する理由」のデータを見てみましょう。このグローバルな統計データは、日本の事業の危機の構造と完全に一致しています。
2-2. 失敗要因1位:「市場ニーズの欠如」
失敗要因の第1位は、「市場ニーズの欠如」、すなわち顧客が欲しがらない、です。
これは、前回の記事で論じた、「技術」や「事業の目的」の論理が、「顧客の利用体験」の論理とバラバラな状態になっていた結果に他なりません。
2-3. 失敗要因2位:「資金枯渇」
そして、第2位が「資金枯渇」、すなわちカネが尽きた、です。
これが、本稿のテーマ「収益化の失敗」そのものです。
なぜ、資金が枯渇するのか。それは、支出(コスト)に見合う「収益(マネタイズ戦略)」を「設計」できていなかったから、「稼ぐ仕組み」がなかったからです。
2-4. 論考:これらは全て「収益設計」の「分断」である
「ニーズがない」、「カネが尽きた」。
この2大失敗要因は、別々の問題ではありません。これらは、「価値」と「価格」の統合設計、すなわち「収益化戦略」の分断が生み出した、必然の「結果」です。
- 失敗要因1位(ニーズがない) = 顧客が「お金を払うほどの価値」を「設計」できていない。(事業と体験の分断)
- 失敗要因2位(資金枯渇) = 顧客が感じている「価値」を、「最適な価格」に「転換(収益化)」する「設計」ができていない。(体験と事業の分断)
「事業実現」とは、この「価値」と「価格」の分断を「統合」し、「顧客が満足して対価を支払い、事業が持続的に成長する“仕組み”」を設計することなのです。
3. 「収益化(事業)」が「分断」される3つのパターン
では、具体的に「収益化」は、どのようにバラバラな状態になり、失敗に至るのでしょうか。
3-1. 分断 1:「事業と体験の分断」—「ユーザー獲得」を優先し、「収益化」を後回しにする
最も典型的で、多くの新しい事業が陥る事業の危機です。「まずはユーザー獲得(体験)に全力を注げ。収益化(事業)は、その“後”で考えればいい」というアプローチです。
- 事例:スタートアップの「広告モデル」の罠 あるスタートアップは、特定のコミュニティサービスを開発し、そのユニークな「体験」は熱狂的に受け入れられ、ユーザー数は爆発的に増加しました。 しかし、彼らは「収益化戦略(事業)」の設計を後回しにしていました。 いざ収益化を試みようと、「広告モデル(事業)」を導入した途端、ユーザーは「純粋なコミュニティ(体験)が汚された」と猛反発。熱狂は冷め、ユーザーは急速に離反しました。
これは、「収益化(事業)」と「顧客体験」がバラバラだった典型的な失敗例です。「稼ぐ」ことと「体験」を「統合」する、優れた「ビジネスモデル設計」が欠如していたために、事業の壁を越えられませんでした。
3-2. 分断 2:「戦略と戦略の分断」—「単一」の収益源に依存し、成長を最大化できない
次に、収益化(事業)には成功しましたが、その「収益モデル」が「一つだけ(例:売り切り)」であるために、「事業の拡張性」が分断されてしまうケースです。
- 事例:ソフトウェア企業の「売り切り」モデルの限界 ある企業は、優れた「パッケージソフト(売り切り)」を開発し、一定の成功を収めていました。 しかし、収益(事業)は「新規顧客の獲得数」に完全に依存しており、常に新規開拓の営業コストに苦しんでいました。 彼らの分断は、「一回限りの収益(売り切り)」と、「継続的な顧客関係(顧客生涯価値)」がバラバラだったことにあります。 競合他社が「月額課金」モデルに移行し、顧客生涯価値を最大化する「継続支援(体験)」に投資する中、この企業は「売り切り」という分断された収益モデルに固執した結果、顧客獲得コストの高騰に耐えきれず、成長が鈍化しました。
3-3. 分断 3:「体験と戦略の分断」—「価格」が「価値」と一致していない
最後に、「戦略(価格設定)」が、顧客が感じる「価値(体験)」とバラバラになっているケースです。
- 事例:複雑すぎる料金体系の悲劇 あるクラウドサービス企業は、非常に多機能な「技術」を持っていました。 その「技術」の複雑さを、そのまま「料金体系(戦略)」に反映してしまいました。 プランA、プランB、オプションC、使った分だけ支払うD… 顧客は、「自分がどのプランを選ぶべきか分からない」という「考えるストレス(体験の悪化)」を感じ、導入(契約)を諦めてしまいました。
これは、「技術」の論理と「戦略」の論理が、顧客の「体験」の論理とバラバラだったために起きた、「事業実現」の失敗です。
4. GREATSの処方箋:「価値(体験)」を「価格(事業)」に「統合」する手法
GREATSは、これらの「収益化の分断」を「統合」し、「稼げる事業(事業実現)」を設計します。
この手法の核は、代表の青山武史が事業再生の現場で「営業利益5倍」や「V字回復」を達成した、事業の採算性を自らの手で作り上げるという「知恵」に基づいています。
4-1. 「問い」の再定義:「いくらか」ではなく「何の対価か」
私たちは、「このサービスは、いくらで売るべきか?」という「価格(戦略)」の問いから始めません。
私たちは、「問い」を再定義します。
「顧客は、我々が提供する“価値”の、一体『何』に対して『対価』を支払う意思があるのか?」
- 「所有」に対してか?(売り切り)
- 「利用(時間)」に対してか?(月額課金)
- 「成果(結果)」に対してか?(成果報酬)
- 「便利さ(体験)」に対してか?(無料提供と有料オプション)
この「価値(体験)」と「価格(事業)」を「統合」する「問い」の再定義こそが、「収益化戦略」の「設計」の第一歩です。
4-2. 手法1:収益化戦略 — 価格設定と収益モデルの設計
「問い」が定義されたら、「稼ぐ仕組み」を具体的に設計します。
- 価格設定戦略: 事例3(複雑な料金)の分断を避けます。顧客が感じる「価値(体験)」と、事業として必要な「コスト」に基づき、「顧客が“迷わず”支払える」最適な価格帯(月額課金、使った分だけ支払う、無料提供と有料オプションなど)を設計します。
- 収益モデルの組み合わせ設計: 事例2(単一収益源)の分断を避けます。「売り切り(初期)」+「月額課金(継続)」+「成果報酬(成功時)」など、複数の収益モデルを組み合わせ、安定した収益基盤(事業)を構築します。
4-3. 手法2:顧客生涯価値の最大化プラン
「収益化」は、「契約(価格)」で終わりではありません。「事業実現(持続可能な事業)」のためには、顧客生涯価値の最大化が不可欠です。
- 自走する仕組みの実現: 代表・青山武史が実践してきた「データに基づいた目標管理」に基づき、「顧客生涯価値が顧客獲得コストの3倍以上」という、事業が「自立して動く」ための「黄金律」を実現する「仕組み」を設計します。
- 「体験(デザイン)」との「統合」: 顧客生涯価値を最大化する(=顧客に「継続」してもらう)鍵は、「顧客体験(体験)」にあります。「一回売って終わり」ではなく、上位サービスへの移行、関連商品の販売、継続利用のための施策を「顧客体験(体験)」と「統合」し、「事業実現」のエンジンを回し続けます。
5. 結論:「収益化設計」こそが、「事業・体験・技術」統合の“要”である
「ユーザーは集まったが、儲からない」(事例1) 「機能はすごいが、儲からない」(事例2) 「価値はあるはずだが、儲からない」(事例3)
これら事業の危機に響くすべての悲鳴は、「収益化戦略(事業)」が、「顧客体験(体験)」や「技術」とバラバラな状態にあることから生まれます。
「収益化(事業戦略)」とは、プロジェクトの「最後」に考える「お金の回収手段」ではありません。
それは、プロジェクトの「最初」に設計されるべき、「価値(体験)」と「技術」を「統合」する「事業実現」の“要”そのものなのです。
GREATSは、「事業実現の設計者」として、この「稼げる仕組み(収益化)」の設計と実行に、どこまでもコミットします。









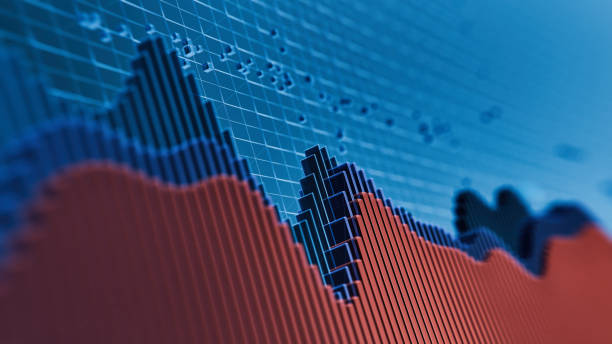
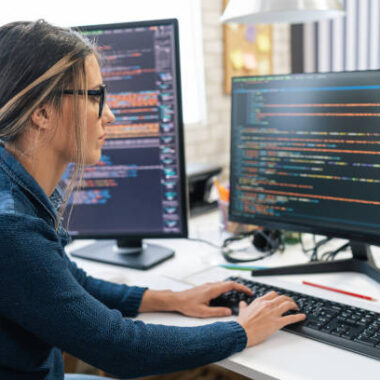




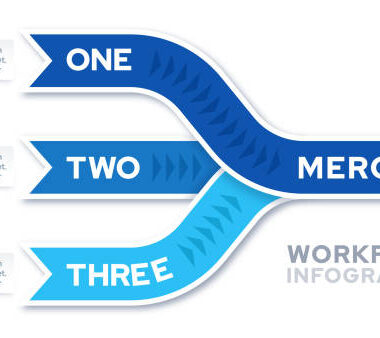





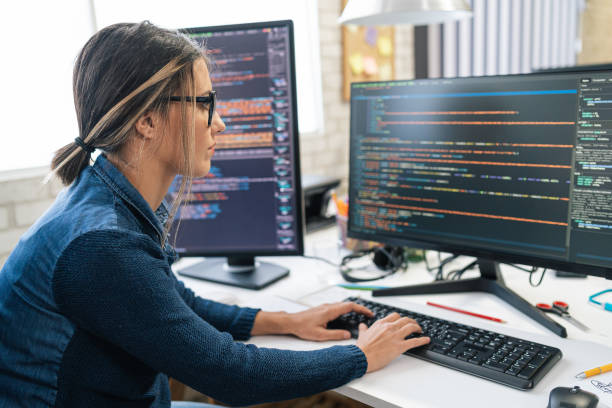



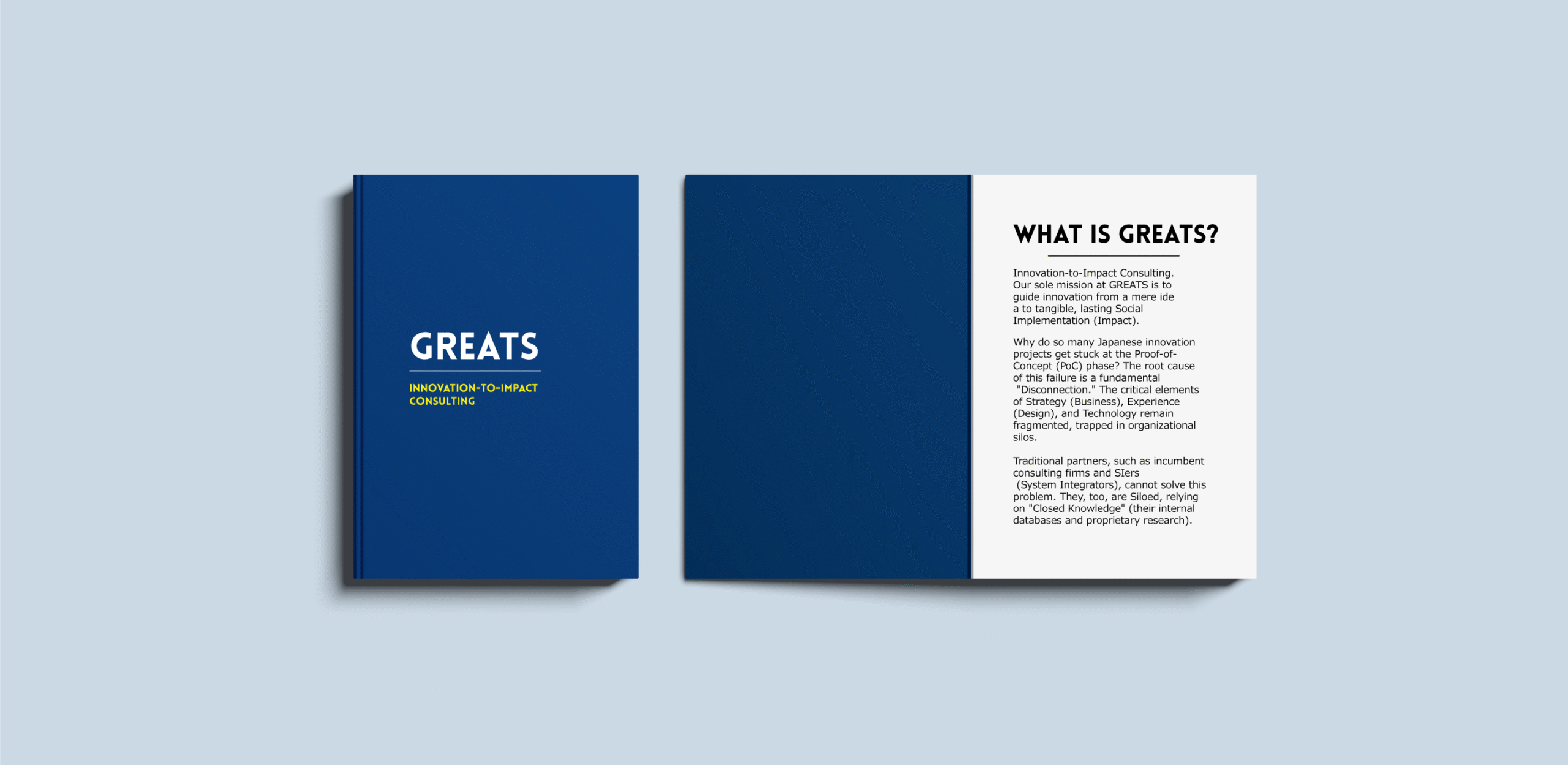
コメント