「技術」と「事業」の「分断」を断つ。「お蔵入り」技術を「事業として実現」する設計図。
日本企業の研究開発(R&D)部門には、世界最高水準の「技術の種」が眠っています。しかし、その多くが「事業部」の論理と**バラバラな状態(分断)**になり、「お蔵入り」となっています。これは「魔の川」「死の谷」と呼ばれる、巨大な機会損失です。本稿では、この「分断」を「統合」し、「技術の種」を「収益を生む事業」へと導く「事業実現」の手法を解説します。
執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部
目次
1. はじめに:「魔の川」「死の谷」という日本の構造的な課題
- 1-1. 「お蔵入り」技術という、日本最大の「機会損失」
- 1-2. イノベーションの障壁:「魔の川」と「死の谷」の定義
- 1-3. 本稿の論点:「技術」と「事業」の“致命的な分断”
2. なぜ「技術の種」は「お蔵入り」になるのか?(分断の仕組み)
- 2-1. 分断 1:「技術オリエンテッド」の罠—「スペック」しか語れないR&D部門
- 2-2. 分断 2:「既存事業」の罠—「コスト」でしか評価できない事業部門
- 2-3. “橋渡し役”の不在:イノベーションが「分断」される瞬間
3. 「自前主義」という「閉じた知恵」の限界
- 3-1. 「魔の川」を越えられない「閉じた」R&D
- 3-2. 「死の谷」を越えられない「閉じた」連携体制
- 3-3. 論考:「自前主義」では「分断」を乗り越えられない
4. GREATSの処方箋:「技術」を「事業」に「統合」するメソッド
- 4-1. 「問い」の再定義:「何ができるか」ではなく「誰の課題をどう稼いで解決するか」
- 4-2. 手法1:技術の事業化支援(設計者としての“翻訳”)
- 4-3. 手法2:連携戦略(「開かれた知恵」の活用)
5. 結論:GREATSは「技術」と「事業」の“事業実現の設計者”である
- 5-1. YKK APの「事業実現」という“証拠”
- 5-2. 「閉じた技術」を「開かれた事業」へ
記事本文
1. はじめに:「魔の川」「死の谷」という日本の構造的な課題
1-1. 「お蔵入り」技術という、日本最大の「機会損失」
日本企業の研究開発(R&D)投資額は、長年にわたり世界最高水準を維持しています。その結果、特に製造業のR&D部門には、世界を変える可能性を秘めた「技術の種(シーズ)」が、**“宝の山”**として眠っています。
しかし、私たちはその“宝”が「事業として実現」され、新たな収益源となった事例を、どれだけ知っているでしょうか。
現実には、その「技術の種」のほとんどが、事業化されることなく研究室の棚や特許の中に「お蔵入り」になっています。
私たちが実績として紹介した「YKK AP」にて直面した、「5年間お蔵入りになっていた次世代素材」は、氷山の一角に過ぎません。この“宝の持ち腐れ”こそが、日本の国際競争力が長期低迷する最大の要因であり、国全体での「機会損失」であると、私たちGREATSは考えています。
1-2. イノベーションの障壁:「魔の川」と「死の谷」の定義
なぜ、日本の優れた「技術の種」は「事業として実現」されないのでしょうか。
この問題は、技術経営の分野において、古くから「2つの障壁」として定義されてきました。リサーチ(客観的な情報)によれば、これらは「魔の川」と「死の谷」と呼ばれています。
- 魔の川: 「基礎研究」と「製品開発」の間にある壁。基礎研究が、市場のニーズと結びつかず、具体的な「製品開発」の段階に進めない障壁。
- 死の谷: 「製品開発」と「事業化(実現)」の間にある壁。製品開発(実証実験)はできたが、それを「収益を生む事業(ビジネス)」として市場に投入するための経営判断(投資)が得られず、プロジェクトが頓挫する障壁。
1-3. 本稿の論点:「技術」と「事業」の“致命的な分断”
本稿では、この「魔の川」と「死の谷」という「障壁」の本質に、GREATSの戦略的な視点である「分断」というメスを入れます。
なぜ、R&D部門は「魔の川」を越えられないのか。 なぜ、新しい事業の部門は「死の谷」で頓挫するのか。
その「病巣」はただ一つ。「技術」を開発する論理と、「事業」を運営する論理が、組織的かつ構造的に**「バラバラな状態(分断)」**になっているからです。
本稿では、この「技術と事業の分断」の具体的な仕組みを解明し、最終的に「お蔵入り技術」を「稼げる事業(事業実現)」へと導く、GREATSの具体的な手法を提示します。
2. なぜ「技術の種」は「お蔵入り」になるのか?(分断の仕組み)
「技術の種」が「魔の川」や「死の谷」で停滞するプロセスは、R&D部門と事業部門の「2つの論理」の分断として、明確に説明できます。
2-1. 分断 1:「技術オリエンテッド」の罠—「スペック」しか語れないR&D部門
第一の分断は、「技術(R&D部門)」側にあります。彼らは、「技術」の論理—すなわち「技術起点」—で動いています。
- 事例:YKK APにおける次世代素材の停滞 私たちが事例で紹介したYKK APの次世代素材プロジェクトは、この「技術オリエンテッド」の典型でした。R&D部門は、この素材の「素晴らしさ」を、「技術の論理(スペック)」で語っていました。「この素材は、鉄の10倍の強度を持ち、重さは10分の1です」。 これは「技術」としては100点満点の成果です。
しかし、彼らの「使命」は「技術を開発すること」であり、「事業を設計すること」ではありませんでした。彼らは「魔の川」を渡るために不可欠な、「市場(顧客)の言語」を持っていなかったのです。
「その技術(スペック)は、“誰の” “どのような課題”を解決し、“なぜ” 顧客は“いくら”払うのか?」
この「事業(ビジネス)」の「問い」が、R&D部門の「使命」と**バラバラな状態(分断)**になっていた。これが「魔の川」の正体です。
2-2. 分断 2:「既存事業」の罠—「コスト」でしか評価できない事業部門
第二の分断は、その「技術の種」の“受け皿”となる「事業部門」側にあります。彼らは、「既存事業(効率化)」の論理—すなわち「既存の仕組み」—で動いています。
- 事例:続・YKK AP—「既存チャネル」の“免疫反応” R&D部門が語る次世代素材の「技術スペック」に対し、事業部門(既存事業)は、以下のような「既存事業の論理(コスト)」で応答しました。「素晴らしい。だが、鉄の50倍のコストがかかるこの素材を、どの顧客(既存の顧客)が買うんだ? 我々の既存の販路では売れない」。
これは、私たちが別の記事で論証した「組織的な抵抗」そのものです。事業部門は、「短期的な利益」と「失敗を許さない評価制度」に最適化されているため、
- 高コスト
- 不確実(儲かるか不明)
- 既存の販路と合わない
という「三拍子」揃った「新しい技術(挑戦)」を、「合理的」に「拒絶(=分断)」したのです。
これが「死の谷」の正体です。「技術(R&D)」と「事業(既存部門)」が、互いに異なる「論理(仕組み)」で動き、「分断」されているために、「事業実現」への道が閉ざされてしまいます。
2-3. “橋渡し役”の不在:イノベーションが「分断」される瞬間
「魔の川」も「死の谷」も、本質は同じです。
「技術(R&D)」の言語(スペック)を、「事業(ビジネス)」の言語(顧客価値、収益化)に「翻訳」し、さらに、その「新規事業(挑戦)」を、「既存事業(効率化)」の「組織的な抵抗」から守るための「仕組み(ルール)」を「設計」する、**「設計者(アーキテクト)」**が「不在」であること。
この「翻訳者」と「設計者」の「不在」こそが、日本の「技術の種」が「お蔵入り」になる、ただ一つの理由なのです。
3. 「自前主義」という「閉じた知恵」の限界
3-1. 「魔の川」を越えられない「閉じた」R&D
この分断を、さらに深刻化させるのが、日本企業(特に製造業)に根強く残る「自前主義(クローズド)」の思想です。
「魔の川」を越える(=技術を製品開発に進める)ためには、その技術の種が、どの「市場ニーズ」と結びつくかを「発見」しなければなりません。
しかし、「自前主義(閉じた知恵)」のR&D部門は、その「ニーズ」を、自社の「既存の顧客」や「既存の市場」の中だけで探そうとしてしまいます。
YKK APの事例で、次世代素材が「既存の販路では売れない」と判断されたのは、まさにこの「閉じた知恵」の罠でした。
彼らは、「自社の外(開かれた世界)」—例えば「先端医療」や「航空宇宙」—といった、その技術を「喉から手が出るほど欲しがる」かもしれない「新しい市場(ニーズ)」に「アクセス」する「手段(ネットワーク)」を持っていなかったのです。
3-2. 「死の谷」を越えられない「閉じた」連携体制
「死の谷」を越える(=事業化する)際も同様です。
次世代素材を「先端医療」で事業化すると決めたとして、YKK AP(建材メーカー)一社(自前主義)で、それが可能でしょうか?
- 医療機器の「顧客(医師)体験」を「設計」できるか?
- 「薬事法」の規制をクリアする「ノウハウ」を持っているか?
- 医療機関への「販売チャネル」を持っているか?
答えは「否」です。「事業実現」とは、自社に「ない」資産(専門性、販路)を、**外部(開かれた仕組み)**から「統合」する「連携戦略」そのものです。
3-3. 論考:「自前主義」では「分断」を乗り越えられない
「自前主義(閉じた知恵)」のままでは、「技術」と「事業」の分断を乗り越え、「魔の川」や「死の谷」を越えることなど、原理的に不可能なのです。
4. GREATSの処方箋:「技術」を「事業」に「統合」するメソッド
GREATSは、この「技術の種のお蔵入り」という「二重の分断(=技術と事業の分断 × 閉じた知恵の分断)」に対し、「事業実現の設計者」として「統合」された「処方箋」を提供します。
4-1. 「問い」の再定義:「何ができるか」ではなく「誰の課題をどう稼いで解決するか」
私たちは、R&D部門(技術)の「スペック」の話から議論を始めません。
私たちは、GREATSの手法に基づき、「問い」を再定義します。
「この技術(種)は、“誰の” “どのような課題(顧客体験)”を解決し、“なぜ” 顧客は対価を支払い、“どう(連携体制)”すれば“持続可能な事業(収益化)”になるのか?」
この「技術」、「体験(デザイン)」、「事業(ビジネス)」を「統合」した「問い」こそが、YKK APの事例で次世代素材を「先端医療」や「発電する建材」という「成功事例(事業実現の解)」へと導いた、GREATS手法の出発点です。
4-2. 手法1:技術の事業化支援(設計者としての“翻訳”)
「問い」を再定義した後、私たちは「設計者」として、そして「翻訳者」として「統合」を実行します。
- 技術の「価値」を「事業」の言語に翻訳する GREATSの手法は、「技術」と「事業」の「バイリンガル」です。R&D部門が語る「技術スペック」を、「事業部門(あるいは投資家)」が理解できる「事業価値(例:既存事業比で20%のコストダウン、新市場での50%のシェア獲得可能性)」へと「翻訳」し、両者の分断された会話を「接続」します。
- 「事業実現」の主要成功要因を特定する 「技術の事業化支援」の核は、この「翻訳」に基づき、「その技術の種が“事業として”成功するための主要成功要因」を特定することにあります。(例:「初期市場は『先端医療』である」「成功要因は『薬事法』のクリアである」「必要なパートナーは『Medi-Venture社』である」)
4-3. 手法2:連携戦略(「開かれた知恵」の活用)
「主要成功要因」が特定されれば、もはや「自前主義(閉じた知恵)」に固執する理由はありません。「事業実現」のために不足している「資産(例:市場、販路、ノウハウ)」を、「開かれた知恵」から調達する段階に移行します。
- 「協会(JOIA)の資産」による「連携体制」の設計 これこそが、GREATSの「競合優位性」です。私たちは、他社のコンサルタントがアクセスできない「協会プラットフォーム」という「開かれた知的資産」を駆使します。 YKK APの事例で、「先端医療」という要因に対し、「48時間」で「京大の研究室」と「専門のベンチャー企業」という「最高の解(ネットワーク)」を「統合」したように。
「連携戦略」とは、この「開かれた知恵」を「統合」し、「事業実現」の「連携体制」を「設計」することに他なりません。
5. 結論:GREATSは「技術」と「事業」の“事業実現の設計者”である
5-1. YKK APの「事業実現」という“証拠”
「技術の種」と「事業」の分断。「自前主義(閉じた知恵)」という分断。
YKK APの事例は、GREATSが、この「二重の分断」を「統合」し、「お蔵入り技術」を「国家規模の事業実現(=発電する建材、疾患リスク発見モデル)」へと導いた、動かぬ“証拠”です。
5-2. 「閉じた技術」を「開かれた事業」へ
「魔の川」や「死の谷」は、越えられない「障壁」ではありません。それは、単なる「分断」です。
GREATSは、 **手法(知恵)**によって、「技術」の言語を「事業」の言語に「翻訳」する。 **資産(開かれた知恵)**によって、「閉じた(自前主義の)技術」を、「開かれた(連携体制の)事業」に「接続」する。
あなたの会社のR&D部門に眠る「お蔵入り技術(技術の種)」を、「事業実現」という「未来の事業」へと「統合」すること。それこそが、GREATSが提供する「技術の事業化支援」の本質です。










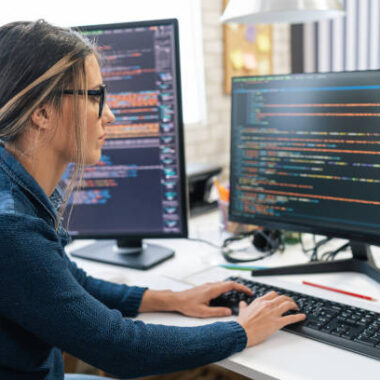












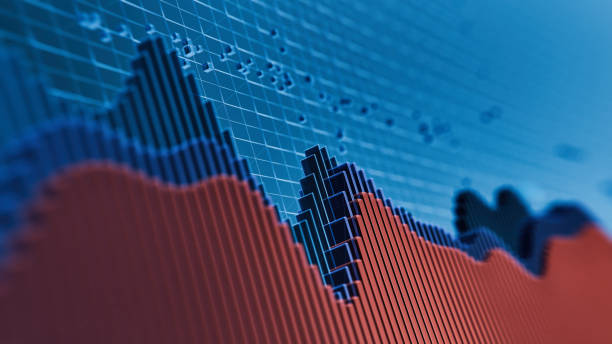

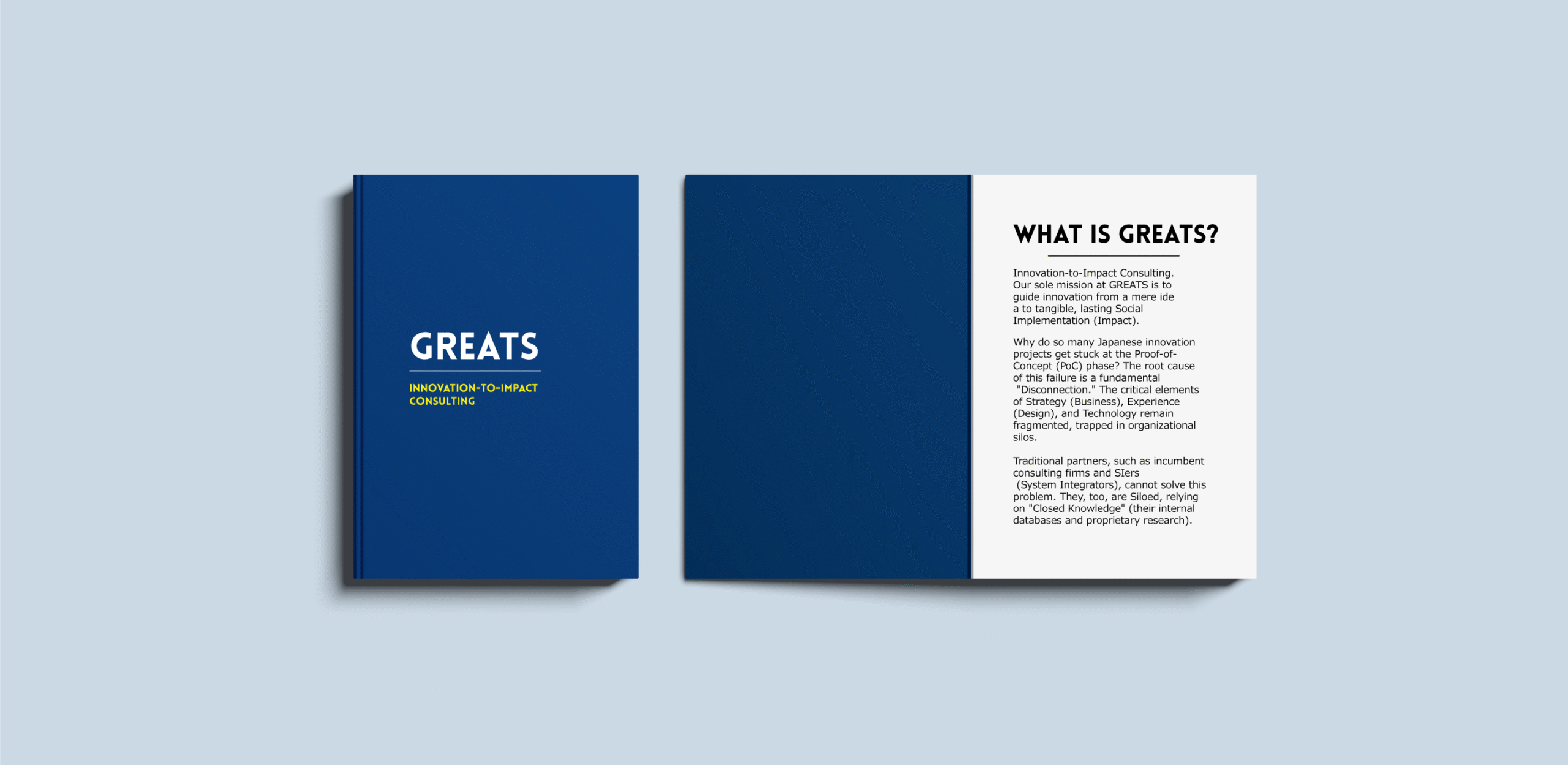
コメント