彼らは「言われたもの」を“実装”する。私たちは「勝てる事業」を“設計”する。
なぜ、巨額の予算を投じた「システム刷新(技術)」は、「変革(DX)」に繋がらないのか。それは、クライアントの「戦略(事業)」や「顧客体験(デザイン)」から**バラバラな状態(分断)**になった「要件定義書(技術)」を、システム構築会社(SIer)が「忠実に」実装しているからです。本稿では、「SIer依存」が「戦略・体験・技術の分断」をいかに“加速”させるかを論証します。
執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部
目次
1. はじめに:「システム実装」≠「事業実現」
- 1-1. DXの“不都合な真実”:なぜ「システム刷新」は「変革」にならないのか
- 1-2. 「システム構築会社(SIer)」という“実装部隊”
- 1-3. 本稿の論点:「技術」と「戦略」の“構造的分断”
2. 「SIer(実装部隊)」の“構造的限界”:「戦略」からの「分断」
- 2-1. 彼らの「目標」は「事業実現」ではなく、「人月」と「納品」である
- 2-2. 「要件定義書」という「分断」の“設計図”
- 2-3. なぜ「要件定義書」通りに作ると「使われないシステム」が生まれるのか
3. 客観的証拠:競合(NTT DATA)が示す「戦略」と「実行」のギャップ
- 3-1. リサーチ分析:「91%」が「古いシステムの壁」に阻まれているという現実
- 3-2. リサーチ分析:戦略(経営層)と現場(技術部門)の「深刻な不一致」
- 3-3. 「SIer依存」モデルの“必然的”な失敗
4. GREATSの処方箋:「実装」の「前」に「統合」を“設計”する
- 4-1. 私たちは「要件定義書」を受け取らない。「問い」を再定義する
- 4-2. 事例(メガバンク):「古いシステム前提」で「事業実現」を設計する
- 4-3. 事例(電力会社):「技術PoC」を「SaaS事業」に“再設計”する
5. 結論:GREATSは「実装部隊」ではなく、「統合」を担う「設計者(アーキテクト)」である
記事本文
1. はじめに:「システム実装」≠「事業実現」
1-1. DXの“不都合な真実”:なぜ「システム刷新」は「変革」にならないのか
前回の記事では、「戦略コンサルタント」の「戦略」が、いかに「実行」から分断され、「絵に描いた餅」に終わるかを論証しました。
では、その「実行」を担う巨大なプレイヤー、すなわち「システム構築会社(SIer)」はどうでしょうか。
日本のDXプロジェクトにおいて、最も巨額の予算が投じられるのは、多くの場合、大手システム構築会社です。彼らは「古いシステム(レガシー)刷新」や「DX基盤構築」を担う、「実装」のプロフェッショナルです。
しかし、彼らが「納品」した「新システム」は、果たして「変革(DX)」、すなわち「新しい事業価値(事業実現)」を生み出しているでしょうか。残念ながら、その多くは、「古いシステム」が「新しいシステム」に入れ替わっただけの、「コスト(刷新)」に終わっていないでしょうか。
なぜ、「システム実装」は、自動的に「事業実現」へと繋がらないのでしょうか。
1-2. 「システム構築会社(SIer)」という“実装部隊”
その理由は、システム構築会社というビジネスモデルの「構造」そのものにあります。
彼らは、クライアントの「戦略(事業)」を設計する「設計者(アーキテクト)」ではありません。彼らは、クライアントから提示された「要件」に基づき、システムを「構築」する**「実装部隊」**です。
彼らの「知恵」は、「戦略(ビジネス)」や「顧客体験(デザイン)」ではなく、「技術(テクノロジー)」の「実装力(マンパワー)」に最適化されているのです。
1-3. 本稿の論点:「技術」と「戦略」の“構造的分断”
本稿は、この「システム構築会社(実装部隊)」の「構造的な限界」に焦点を当てます。「システム実装」のプロである彼らは、その「専門性」ゆえに、
- 「経営戦略(ビジネス)」から**「分断」**され、
- 「顧客体験(デザイン)」から**「分断」**されている。
本稿では、「SIer依存」が分断をいかに“加速”させるか、そのメカニズム(=要件定義書の罠)を解明します。
2. 「SIer(実装部隊)」の“構造的限界”:「戦略」からの「分断」
2-1. 彼らの「目標」は「事業実現」ではなく、「人月」と「納品」である
システム構築会社のビジネスモデルの根幹は、「人月」、すなわち「何人のエンジニアが、何ヶ月働いたか」で売上(フィー)が決定される「請負契約」です。
これは、彼らの「目標(KPI)」が、「クライアントの事業が『事業実現』されたか(=成果)」ではなく、「『要件定義書』通りのシステムを『期日通り』に『納品』**できたか(=作業完了)」であることを意味します。
彼らの「知恵」は、「成果(事業実現)」を最大化するためではなく、「作業(マンパワー)」を「効率的」に「管理」するために最適化されているのです。
2-2. 「要件定義書」という「分断」の“設計図”
この「請負(人月)」モデルにおいて、クライアントとシステム構築会社を繋ぐのが、「要件定義書」です。しかし、この「要件定義書」こそが、**「分断」の“設計図”**そのものです。
私たちがDX戦略に関する記事で論じた通り、クライアントの多くは、「戦略(事業)」を「技術」に「翻訳」する「設計力」を社内に持っていません。その分断されたクライアントが作成する「要件定義書」は、必然的に分断されています。
「戦略(ビジネス)」部門の「理想」と、「技術(テクノロジー)」部門の「制約」などが「統合」されていない「矛盾(分断)」を孕んだまま、「要件定義書」は作られます。
2-3. なぜ「要件定義書」通りに作ると「使われないシステム」が生まれるのか
「実装部隊」であるシステム構築会社は、この分断された「要件定義書」を「正」として受け取り、「忠実に(契約通りに)」システムを「実装」します。
その結果、何が起きるか。私たちが「高機能・低UX」に関する記事で論じた「悲劇」です。
- 「戦略」と「技術」の分断:「戦略(ビジネス)」の「あるべき論」と、「技術」の「現実(古いシステム)」が分断されたまま実装され、「絵に描いた餅」が生まれる。
- 「体験」と「技術」の分断:「顧客体験(デザイン)」の視点が欠如した「要件定義書」に基づき、「技術」の論理だけで実装され、「高機能だが使われない」システムが生まれる。
システム構築会社は「契約違反」を犯していません。彼らは「分断された設計図」通りに「実装」しただけです。「SIer依存」とは、分断を解決するどころか、自社の分断を「システム」として「固定化・加速」させてしまう、極めて危険なアプローチなのです。
3. 客観的証拠:競合(NTT DATA)が示す「戦略」と「実行」のギャップ
この「戦略」と「技術(実行)」の「分断」は、システム構築業界の巨人であるNTT DATA自身が「客観的データ」として提示しています。
3-1. リサーチ分析:「91%」が「古いシステムの壁」に阻まれているという現実
NTT DATAが行った調査は、「91%」の企業が、「**古いシステム(レガシー)**が、新しい技術(AIなど)の活用能力に重大な影響を与えている」と回答している事実を示しています。
これは、「技術(古いシステム)」が、新しい「戦略(AI活用)」の“足枷”となっている、典型的な「技術と戦略の分断」の“証拠”です。
3-2. リサーチ分析:戦略(経営層)と現場(技術部門)の「深刻な不一致」
さらに、NTT DATAの別の大規模調査は、「戦略(経営層)」と「実行(現場・技術)」の分断を明らかにしています。
- 戦略(CEO)は楽観的:CEOの67%がAIに「重大なコミットメント」を計画。
- 実行(技術部門)は懐疑的:一方で、技術責任者の45%が、AI導入に「ネガティブな感情」を抱いている。
- 分断の理由:技術責任者の54%が「内部のルールや仕組み(=ガバナンス)が不明確」であると回答しているにもかかわらず、CEOで同様の懸念を持つのはわずか20%でした。
これは、NTT DATA自身のリサーチが、経営層(戦略)と現場(技術・組織)の間に「深刻なギャップ」と「不一致」が存在することを立証した、決定的な「証拠」です。
3-3. 「SIer依存」モデルの“必然的”な失敗
これらのデータは、「システム構築会社(実装部隊)」が直面する「構造的な限界」を示しています。
彼らは、「分断」されたクライアント(=戦略と現場の「不一致」)から、「分断」された「要件定義書」を受け取り、「分断」された(=古いシステムの壁を前提とした)「実装」を行わなければならない。このモデルでは、変革(DX)が失敗し、「事業実現」に至らないのは“必然”なのです。
4. GREATSの処方箋:「実装」の「前」に「統合」を“設計”する
4-1. 私たちは「要件定義書」を受け取らない。「問い」を再定義する
GREATSは、この「SIer依存」モデルとは対極にあります。私たちは「実装部隊」ではありません。「事業実現の設計者(アーキテクト)」です。
私たちは、クライアントから分断された「要件定義書」を「受け取らない」。私たちは、その「要件定義書」の「前提」となった「問い」そのものを「再定義」します。
「どのシステムを刷新(技術)しますか?」という「実装部隊の問い」ではなく、「あなたの会社の『経営戦略』と『顧客体験』を阻害している『技術的な“分断”』はどこですか?」という「設計者の問い」を立てるのです。
4-2. 事例(メガバンク):「古いシステム前提」で「事業実現」を設計する
「メガバンク」の事例は、この「設計者」の仕事を象徴しています。
- 実装部隊の「解」:「古いシステム(技術)」を「刷新(実装)」するために「5カ年計画」を提案した(=「分断」された「技術」の解)。
- GREATSの「解」:「古いシステムは“前提”として、どう“最速で”『パーソナライズ戦略(戦略)』を『事業実現』するか?」という問いに再定義しました。そして、「二つの仕組みの共存(組織設計)」と、「外部(FinTech)との連携(技術統合)」という「事業実現の設計図」を描いたのです。
私たちは「実装」したのではありません。「事業実現」の「設計(アーキテクチャ)」を「設計」したのです。
4-3. 事例(電力会社):「技術PoC」を「SaaS事業」に“再設計”する
「大手電力会社」の事例も同様です。
- 実装部隊の「解」:「AI(技術)で何ができるか?」という「技術PoC(実証実験)」を回し続け、分断を加速させていました。
- GREATSの「解」:「AI(技術)」を「手段」とし、「SaaS事業(戦略)」という「第二の収益源」を「目的」として「再設計」しました。そして、「戦略(ビジネス)」と「体験(デザイン)」を「統合」した「事業実現の設計図」を描いたのです。
5. 結論:GREATSは「実装部隊」ではなく、「統合」を担う「設計者(アーキテクト)」である
「古いシステムの壁」は、「技術」の課題であると同時に、「戦略(事業)」と「組織(デザイン)」の分断の課題です。
**「システム構築会社(実装部隊)」**は、その「ビジネスモデル(請負・人月)」の「構造的な限界」により、「技術」のプロではあっても「戦略」と「体験」のプロではありません。
彼らに分断された「要件定義書」を渡すことは、分断そのものを「実装」し、固定化させる行為に他ならないのです。
**「GREATS(設計者)」**は、「実装」ではなく「設計」で勝負します。
私たちは、
- **「統合」された「手法(知恵)」**により、
- クライアントが「要件定義書」を書く“以前”の段階で、「戦略・体験・技術」を「統合」する「事業実現の設計図(アーキテクチャ)」を描きます。
あなたの会社に必要なのは、「要件定義書」通りに「実装」する「実装部隊」でしょうか?それとも、「事業実現」そのものを「設計」する「設計者」でしょうか?
GREATSは、後者のための「解」です。






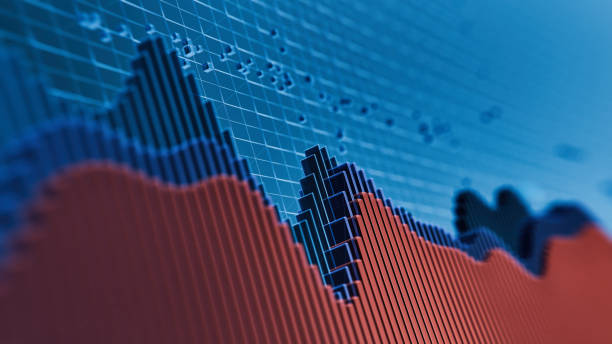



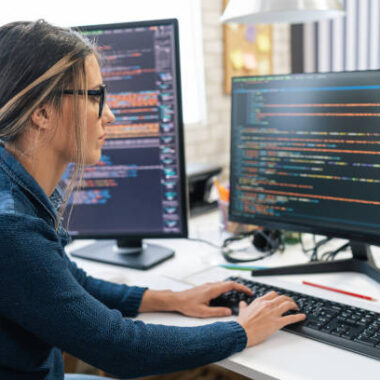













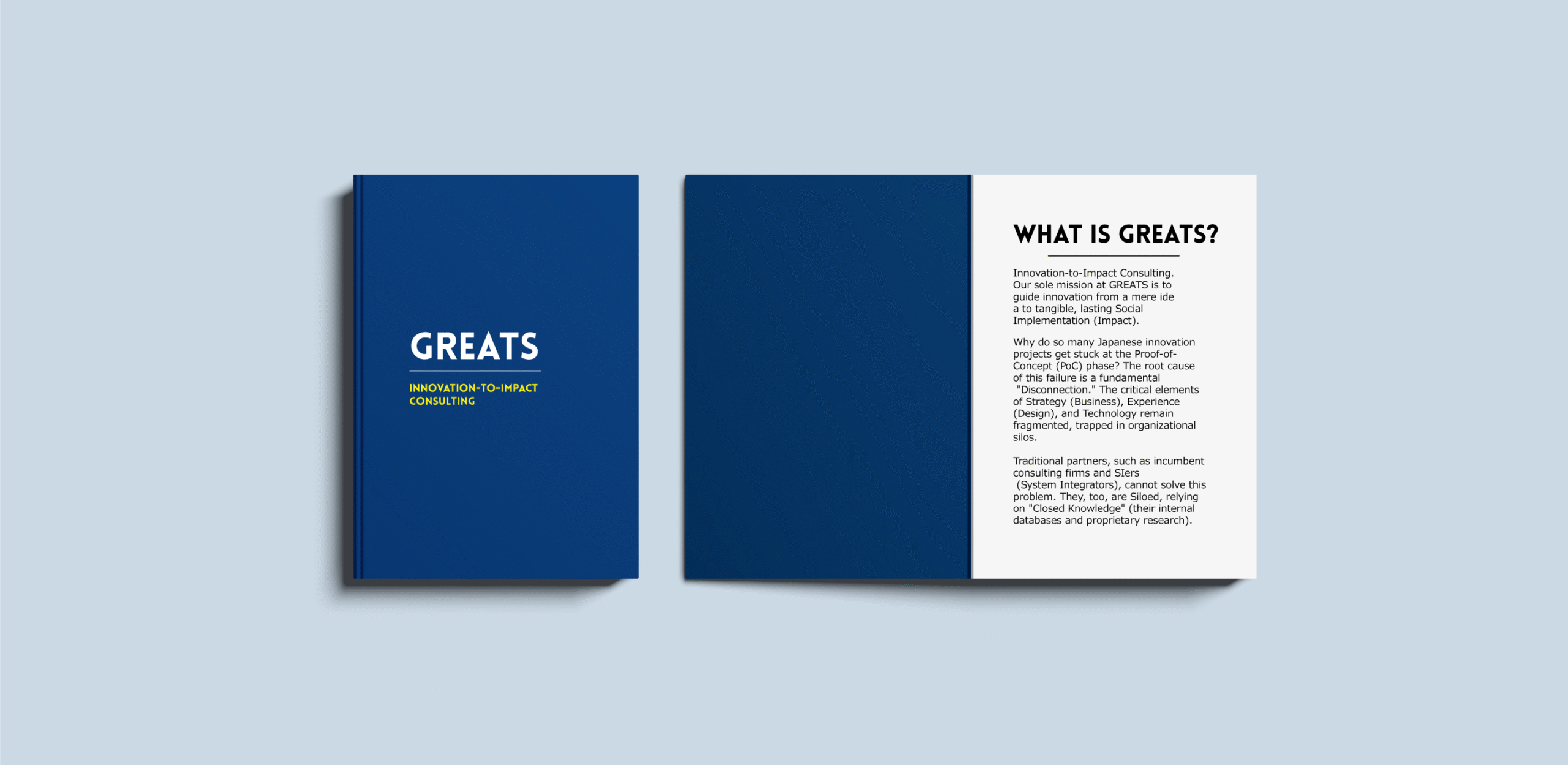
コメント