社会実装を成し遂げる、現代のイノベーション論。
シュンペーターはイノベーションを「新結合」と定義した。しかし、現代の「新結合」とは単なる技術革新ではない。私たちは、稼げる「事業」、顧客を熱狂させる「体験」、実現可能性を担保する「技術」の3つを**「統合」するプロセス**そのものだと再定義し、その戦略的必然性を論証します。
執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部
目次
- はじめに:シュンペーターの「新結合」と、現代の「分断」
- 1-1. イノベーションの父、シュンペーターの功績
- 1-2. 現代の「新結合」が失敗する理由:「分断」という現実
- 1-3. GREATSの再定義:イノベーション = 3領域の「統合」
- 分断の悲劇 1:「事業(ビジネス)」が欠けた場合
- 2-1. 症状:「魔の川」「死の谷」を越える「稼ぐ力」の欠如
- 2-2. ケーススタディ:素晴らしい技術が「お蔵入り」する(R&D部門の罠)
- 2-3. ケーススタディ:熱狂的な体験が「マネタイズ」できない(スタートアップの罠)
- 2-4. 論考:なぜ「事業(ビジネス)」が「統合」の起点となるのか
- 分断の悲劇 2:「組織・体験(デザイン)」が欠けた場合
- 3-1. 症状:「高機能だが使われない」「組織の壁に阻まれる」
- 3-2. ケーススタディ:「高機能・低UX」と「顧客体験」の分断
- 3-3. ケーススタディ:「戦略」と「組織文化(組織デザイン)」の分断
- 3-4. 論考:「体験(デザイン)」こそが「社会実装」のインターフェースである
- 分断の悲劇 3:「技術(テクノロジー)」が欠けた場合
- 4-1. 症状:「戦略」が「絵に描いた餅」で終わる
- 4-2. ケーススタディ:「戦略」と「レガシーシステム」の分断
- 4-3. ケーススタディ:「体験」と「技術的実現性」の分断
- 4-4. 論考:「技術」は「手段」ではなく「戦略基盤」である
- 結論:GREATSが「社会実装のアーキテクト」を名乗る理由
- 5-1. 「統合」こそが、現代の「新結合」である
- 5-2. アーキテクトの役割:3領域を「統合」して設計する
記事本文
1. はじめに:シュンペーターの「新結合」と、現代の「分断」
1-1. イノベーションの父、シュンペーターの功績
ヨーゼフ・シュンペーターが、その著書『経済発展の理論』において「イノベーション」を「新結合」と定義して一世紀以上が経過しました。
彼が定義した新結合とは、単なる発明とは異なります。それは、
- 新しい生産物の創出
- 新しい生産方法の導入
- 新しい販路の開拓
- 新しい資源の獲得
- 新しい組織の形成
といった、既存の知や資源を**「結合」させ、市場に新たな価値と経済的利益を生み出す「経済活動」**そのものを指しました。
この定義は、現代においてもイノベーションの本質を鋭く突いています。私たちが目にするイノベーションの多くは、全くのゼロから生まれたものではなく、既存の何かと何かの「新しい組み合わせ」によって生まれているからです。
1-2. 現代の「新結合」が失敗する理由:「分断」という現実
しかし、です。
シュンペーターの時代から100年が経過し、企業組織は巨大化・複雑化し、技術は高度化しました。その結果、現代の新結合は、かつてないほどの困難に直面しています。
前回のインサイト記事で私たちが論証したように、現代の日本企業は分断という深刻な構造的課題を抱えています。
- 事業戦略を考える部門
- 組織や顧客体験のデザインを考える部門
- テクノロジーすなわち技術を考える部門
これらが、厚い「組織の壁」、すなわちサイロによって分断されています。
シュンペーターが提唱した新結合を実行しようにも、結合すべき「知」そのものが組織内で分断され、出会うことすらできません。これが事業化に至らない実証実験や、いわゆる「死の谷」を生み出す本質的な病巣です。
1-3. GREATSの再定義:イノベーション = 3領域の「統合」
だからこそ、私たちGREATSは、シュンペーターの定義を現代の文脈に合わせて「再定義」する必要があると考えています。
現代における新結合とは、単なる技術革新や目新しいビジネスモデルの創出を指すのではない。
私たちは、
- 稼げる事業(ビジネスモデル)
- 顧客を熱狂させる体験(デザイン)
- 実現可能性を担保する技術(テクノロジー)
の3領域を、意図的に**「統合(Integration)」するプロセス**そのものこそが、現代における新結合であると再定義します。
なぜなら、この3領域のどれか一つでも欠ければ、すなわち分断されれば、イノベーションは「社会実装」というゴールに決して辿り着けないからです。
本稿では、この「事業・体験・技術」の各領域が「分断」された時に、具体的にどのような「失敗(=死の谷)」が待ち受けているのかを、ケーススタディを通じて徹底的に解明します。そして、なぜGREATSがこの3領域の**「統合」**をミッションとするのか、その戦略的必然性を論証します。
2. 分断の悲劇 1:「事業(ビジネス)」が欠けた場合
2-1. 症状:「魔の川」「死の谷」を越える「稼ぐ力」の欠如
イノベーションの3つの分断の中で、最も致命的かつ初歩的な失敗は、「事業(ビジネス)」—すなわち「事業戦略」や「マネタイズ戦略」—の欠如です。
素晴らしい「技術」が生まれた。あるいは、熱狂的な「体験」がデザインされた。しかし、「で、それをどうやって『事業』にするのか?」という問いに答えられない。
これは、まさに「魔の川」(研究が製品開発に進まない)や「死の谷」(開発が事業化に進まない)でプロジェクトが頓挫する最大の原因です。
2-2. ケーススタディ:素晴らしい技術が「お蔵入り」する(R&D部門の罠)
前回のインサイト記事でも触れた「大手化学メーカーA社の『お蔵入り』AI」の事例は、この「事業と技術の分断」の典型です。
A社のR&D部門は、世界最高水準のAI技術(技術シーズ)を開発しました。しかし、彼らのミッションは技術を開発することであり、事業を設計することではありませんでした。
彼らが魔の川を渡ろうとした時、事業部門は「その技術は高コストすぎて儲からない(マネタイズできない)」という「既存事業の論理」でそれを評価しました。
結果、この新結合の種であるAI技術は、既存の知である既存事業の収益モデルと結合することを拒否され、死を迎えました。
この失敗の本質は、AI技術の開発プロセスに、事業戦略の視点—例えば、「この技術を活かせる新しい(既存事業とは異なる)ビジネスモデルは何か?」や「どの市場セグメントならば、このコストでも『価値』を感じてくれるか?」—が**「統合」されていなかった**ことにあるのです。
2-3. ケーススタディ:熱狂的な体験が「マネタイズ」できない(スタートアップの罠)
この「事業(ビジネス)」の欠如は、大企業R&D部門だけの専売特許ではありません。多くのスタートアップが陥る「死の谷」でもあります。
【ケーススタディ:SNS系スタートアップJ社の「熱狂と赤字」】
J社は、特定のコミュニティに特化したSNSサービスを開発しました。そのユニークな「体験」は熱狂的に受け入れられ、ユーザー数は爆発的に増加。メディアにも「次世代のFacebook」と取り上げられました。
しかし、彼らは「まずはユーザー数を集めること」を優先し、「マネタイズ戦略(事業)」の設計を後回しにしていました。
いざ収益化(事業)を試みようと、安易に「広告モデル」を導入した途端、ユーザーは「純粋なコミュニティ(体験)が汚された」と猛反発。熱狂は冷め、ユーザーは急速に離反しました。
J社は、「体験」と「事業」を「統合」する(=ユーザー体験を損なわずに収益を上げる)ビジネスモデルを設計できなかったため、「死の谷」を越えられず、資金ショート(倒産)に至ったのです。
2-4. 論考:なぜ「事業(ビジネス)」が「統合」の起点となるのか
技術も体験も、それ自体は「価値」を生み出しますが、「事業(ビジネス)」を生み出すとは限りません。
「事業」とは、持続可能な**「社会実装」そのもの**です。「稼ぐ力(=マネタイズ戦略)」を欠いたイノベーションは、どれほど素晴らしくとも、いずれリソースが尽きて消滅する運命にあります。
だからこそ、私たちGREATSは、「事業(ビジネス)」を、イノベーション**「統合」の「起点」**に据えるのです。
「その技術は、どう稼ぐのか?」
「その体験は、どう稼ぐのか?」
この問いを、プロジェクトの初日(魔の川の手前)から発し続けること。それこそが、「死の谷」を越えるための唯一の地図、すなわち社会実装ロードマップを描くことに繋がるのです。
3. 分断の悲劇 2:「組織・体験(デザイン)」が欠けた場合
3-1. 症状:「高機能だが使われない」「組織の壁に阻まれる」
次に、たとえ「戦略(事業)」と「技術」が完璧に結びついていたとしても、「デザイン」の視点が欠如しているために失敗するケースを見ていきましょう。
ここでいう「デザイン」は、狭義の「見た目」だけを指すのではありません。
それは、
- **「顧客体験(Customer Experience)」**と、
- それを支える**「組織体験(Employee Experience)」**、すなわち組織プロセス
という、2つの「体験」のデザインを意味します。
「事業と技術の分断」が「死の谷」の主因だとすれば、「デザインの分断」は、その後の「ダーウィンの海」(市場での淘汰)で敗北する主因であり、また、そもそも「死の谷」を越えるための推進力を失わせる**「組織の壁」の主因**でもあります。
3-2. ケーススタディ:「高機能・低UX」と「顧客体験」の分断
前回のインサイト記事でも紹介した「大手通信C社の『多機能』サービス」や「大手ヘルスケアH社の『現場無視』システム」は、この「技術と顧客体験の分断」の典型例です。
C社は、「技術」の論理(実装できる機能はすべて実装する)を優先し、「顧客」の論理(本当に欲しい体験は何か)を無視しました。
H社は、「技術」の論理(AIによる効率化)を優先し、「現場」の論理(医師のワークフロー)を無視しました。
どちらも、戦略(事業)として「儲かる」はずでした。技術的にも「実現」できていました。
しかし、たった一つの**「顧客体験のデザイン」の欠如**—すなわち「使う人間」の視点の欠如—によって、市場(顧客)から拒絶され、「ダーウィンの海」で淘汰されました。
「社会実装」とは、社会(=人間)に受け入れられることです。
「顧客体験のデザイン」とは、戦略(事業)と技術を、「人間(顧客)」が受け入れ可能な**「形」に翻訳・実装する、不可欠な「インターフェース」**なのです。
3-3. ケーススタディ:「戦略」と「組織文化(組織デザイン)」の分断
「デザイン」のもう一つの側面、「組織デザイン(組織・プロセス・文化)」の欠如は、さらに深刻な「分断」を生みます。
前回のインサイト記事で紹介した「大手金融B社の『イノベーション部門の孤立』」や「大手製造業M社の『営業チャネルの壁』」は、まさにこれです。
B社は、新しい「戦略(事業)」を実行するために「イノベーション部門」を作りましたが、既存の「組織」、すなわち既存事業部門の評価制度やガバナンスをデザインし直すことを怠りました。
M社は、新しい「戦略(事業)」であるサブスクリプションを実行するために、既存の「組織」である代理店販売網の利害を調整する**「プロセス」をデザインしなかった**。
どちらも、戦略(事業)と組織(デザイン)が「分断」されていたために、社内の**「組織的な抵抗」**によってプロジェクトが拒絶されました。
これは、イノベーションが「社会」に実装される以前に、「社内」で実装(=合意形成)できなかったことを意味します。
3-4. 論考:「体験(デザイン)」こそが「社会実装」のインターフェースである
事業戦略がイノベーションの推進力であるならば、デザインは社会と接続するための**「接点」**です。
推進力(事業)がいかに強力でも、顧客体験という「接点」が市場のニーズと噛み合っていなければ、空転するだけです。
また、組織デザインという「接点」が「組織の壁」でロックされていては、そもそも前進(社会実装)することすらできません。
「体験(デザイン)」とは、戦略(事業)や技術という「内部の論理」を、社会(顧客・組織)という「外部の現実」と接続(=統合)させるための、**極めて重要な「社会実装のインターフェース」**なのです。
4. 分断の悲劇 3:「技術(テクノロジー)」が欠けた場合
4-1. 症状:「戦略」が「絵に描いた餅」で終わる
最後に、現代において急速に重要性を増している、「技術(テクノロジー)」の欠如による「分断」です。
素晴らしい「戦略(事業)」が描かれ、完璧な「顧客体験(デザイン)」がデザインされたとしても、「技術」の裏付けがなければ、それはすべて「絵に描いた餅」に終わります。
4-2. ケーススタディ:「戦略」と「レガシーシステム」の分断
前回のインサイト記事でも紹介した「大手金融F社の『レガシーの足枷』」は、この「戦略と技術の分断」を象徴しています。
F社は「若年層向けのシームレスな金融体験(戦略)」を描きました。しかし、その戦略は、自社が抱える「勘定系レガシーシステム(技術)」の技術的制約を無視していました。
「戦略」と「技術」が「分断」されていたため、実証実験は「技術的実現性なし」として頓挫しました。
これは金融業界に限らず、製造業の基幹システム、小売業の在庫管理システムなど、あらゆる業界で「レガシーシステム(技術的負債)」がイノベーションの足枷となっています。
「DX戦略」とは、まさにこの**「戦略と技術の分断」を「統合」**し、レガシー(技術)を「攻め」の戦略基盤へと再構築する試みそのものです。
4-3. ケーススタディ:「体験」と「技術的実現性」の分断
【ケーススタディ:大手百貨店G社の「魔法のアプリ」】
G社(百貨店)は、「オンラインとオフラインの完全な融合(OMO)」という顧客体験(デザイン)を構想しました。
そのアプリ(実証実験)は、「店舗の在庫とリアルタイムで連携し、AIが顧客の好みに合わせて接客員を推薦、シームレスに決済できる」という、まさに「魔法」のような体験をデザインしました。
しかし、G社の「技術基盤(テクノロジー)」は、この「魔法」を実現するにはあまりにも脆弱でした。
在庫データはリアルタイム連携(技術)されておらず、AI(技術)の精度も低く、決済システムもアプリ(技術)と「分断」されていたのです。
結果、デザイン(体験)部門が描いた「理想の体験」は、技術部門によって「実装不可能」と判断され、プロジェクトは大幅に縮小。「魔法」は「平凡な」アプリへと成り下がってしまいました。
4-4. 論考:「技術」は「手段」ではなく「戦略基盤」である
かつて「技術」は、「戦略(事業)」部門が決めたことを実行する「手段」であり「コストセンター」でした。
しかし、現代において「技術」は、戦略(事業)の選択肢そのものを定義し、体験(デザイン)の実現可能性を左右する、「戦略基盤」そのものです。
「その戦略、技術的に実現できるのか?」
「その体験、技術的にスケールできるのか?」
この問いを抜きにしたイノベーションは、すべて「絵に描いた餅」に終わります。
「技術」とは、「戦略(事業)」と「体験(デザイン)」を「統合」し、「社会実装」という「現実」に落とし込むための**「土台」**なのです。
5. 結論:GREATSが「社会実装のアーキテクト」を名乗る理由
5-1. 「統合」こそが、現代の「新結合」である
本稿で見てきたように、イノベーションの失敗(実証実験どまり、死の谷、ダーウィンの海)は、ほぼすべて「戦略・組織・技術」の**「分断」**に起因します。
- 「事業」が欠ければ、プロジェクトは「死の谷」を越える「稼ぐ力」を失う。
- 「組織・体験」が欠ければ、「組織の壁」に阻まれるか、「市場」で淘汰される。
- 「技術」が欠ければ、戦略は「絵に描いた餅」に終わる。
シュンペーターが提唱した「新結合」が、もし現代において「分断」によって機能不全を起こしているのだとしたら、私たちが今なすべきことは明らかです。
**「事業・デザイン・技術の『統合』」**こそが、現代における「新結合」であり、イノベーションを「社会実装」するための唯一の解なのです。
5-2. アーキテクトの役割:3領域を「統合」して設計する
私たちGREATSが「社会実装のアーキテクト(設計者)」を名乗る理由は、ここにあります。
私たちは、事業・体験・技術の「どれか」の専門家ではありません。
私たちは、事業・体験・技術の**「すべて」を「統合」する専門家**です。
私たちは、クライアントが抱える「分断」の構造を見抜き、
- 「戦略」と「組織」を「統合」し、
- 「戦略」と「技術」を「統合」し、
- 「体験」と「技術」を「統合」する。
この**「統合」の設計図**を描き、その実行を最後まで「伴走」すること。
それこそが、GREATSが提供する唯一無二の価値なのです。










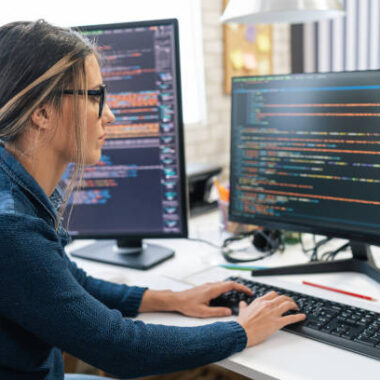









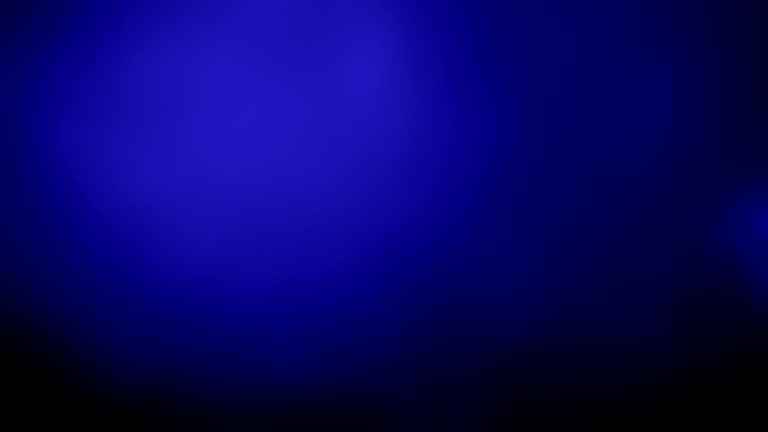


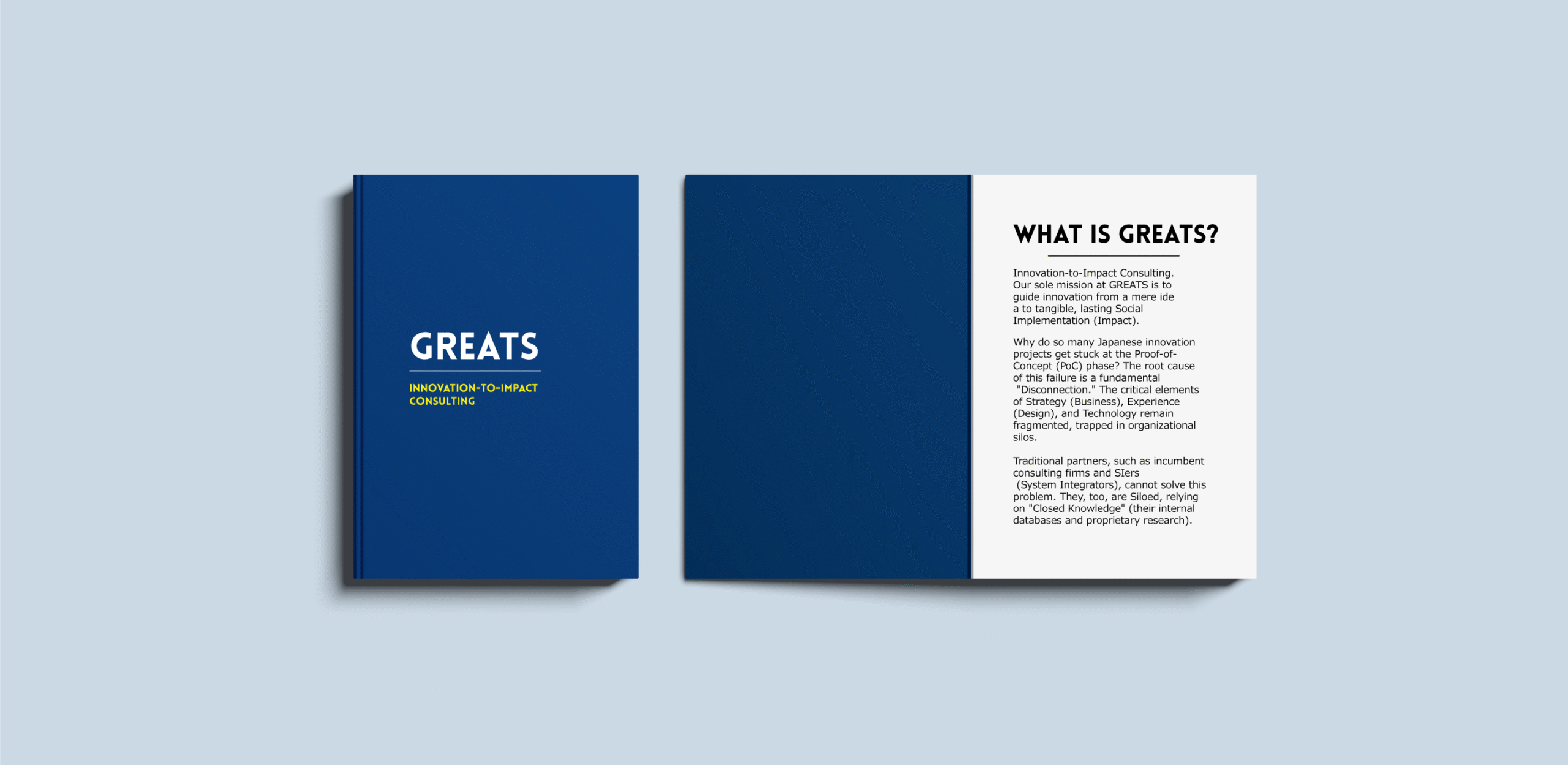
コメント